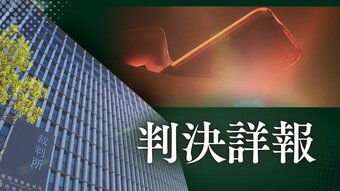戦争の記憶を後世に伝える「戦争遺跡」 終戦から80年近くが経ち、その多くが老朽化や再開発などによって消滅の危機に直面しています。こうしたなか、かつて東洋一といわれる軍事施設があった町が、クラウドファンディングを活用した保存に乗り出しました。
◆高さ7メートルあまり、幅36メートルの格納庫

福岡県筑前町高上地区にある高さ7メートルあまり、幅36メートル近くにのぼる「掩体壕」
「掩体」は戦時中、敵の空襲から軍用機を守るために造られた格納庫です。

大刀洗平和記念館 尾籠浩一郎館長「当時の戦闘機でいえば2機が入るくらいの広さで、この規模の掩体豪はちょっとあまり残っていません」
かつて特攻の中継基地だった大刀洗飛行場の周辺にも数多く造られましたが、終戦から78年が経ち老朽化が進んでいます。
大刀洗平和記念館 尾籠浩一郎館長
「コンクリートなので少しでもひびがあればそこから雨水が浸透していって、中の鉄筋を腐食させるということになりますのでやはりいずれは潰れてしまう可能性が高いです」
◆若き特攻隊員が出撃した

1919年、福岡県の筑前町と大刀洗町、朝倉市にまたがる場所に、国内4か所目の陸軍飛行場として開設された「大刀洗飛行場」。その規模は当時、「東洋一」とも言われ、多くの若き特攻隊員たちが出撃していきました。しかし、1945年3月。2度にわたるアメリカ軍機の空襲を受けます。投下された爆弾は約2400発。集団下校中の幼い子供など1000人を超える尊い命が奪われたとされています。

◆当時20歳の人も98歳に 語る人がいない

大刀洗平和記念館 尾籠浩一郎館長
「(終戦から)78年で再来年で戦後80年を迎える時期が来ております。当時20歳の方でも98歳ということで現実に人の言葉として語りかけるのが難しい。戦争遺跡は戦争を語る実物として大変貴重なものだと感じています」
◆物言わぬ語り部「戦争遺跡」も年々減少

戦争を体験した人が年々減っていくなか、その記憶を伝えていくため、戦争遺跡の重要性は高まっています。福岡県教育委員会が2017年度から3年間にわたって文献などを調査した結果、県内で確認された戦争遺跡は624件にのぼります。しかし、老朽化や開発などを背景に年々その姿は失われ、筑前町の掩体も今では1基だけとなっています。
大刀洗平和記念館 尾籠浩一郎館長
「少しでも町のほうで保存を考えている。できることはやっていくということで今考えています。悲惨な戦争の記憶を風化させてはいけない」。