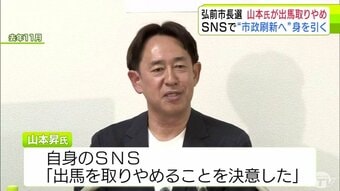お盆の時期になると青森県の一部地域で店頭に並ぶ商品があります。それがこちら。


パッケージには「とうろう」の文字、よく見るとモナカの皮のようなものでできていますが、パッケージの裏には「食べられません」の表記があります。これはいったい何に使うものなのでしょうか。
市内で聞いてみました。
「…知ってます。お盆とうろうっていうんだよ。飾ったもんだよ、仏さんに」
「うちは昔から、お盆で使ってますね」
「うちは下北(地方)ですが、お盆のとき使ってます。」


どうやらお盆に使われるモノのようです。
そこで地域の風習に詳しい、青森県立郷土館学芸員の増田さんに聞いてみました。
北海道や青森県の一部などで使用されるもの
青森県立郷土館 学芸員 増田公寧さん
「これは、お盆の頃に、墓前や仏壇に吊るして飾る「とうろう」と呼ばれるものです。私の実地調査によりますと、北海道から青森県の津軽地方と下北地方、秋田県、山形県の庄内地方で使われているようです。よく見ると野菜や果物の形をしたものもありますが、元々は畑で採れた作物とか山で採れた産物を仏様にお供えするという、供物の代用品として作られたものなんです」


「とうろう」は、仏壇や墓の盆棚の前に渡した棒や縄に、吊るして飾ります。地域によっては、ホオズキやそうめん、昆布を一緒に飾ったりもするそうです。墓前や仏壇を美しくにぎやかに飾り、盆に来る霊をもてなす気持ちが、極彩色の派手な色使いや形態の多様化を促したのだろうと増田さんはいいます。
「とうろう」の製造工場に行ってみた
この「とうろう」を製造しているのが、青森県鶴田町のサトウ商事です。サトウ商事は、正月のしめ飾りやお盆用品の製造卸の会社です。「とうろう」の出荷準備に追われている中、工場を見学させていただきました。


原材料はコーンスターチともち米と着色料など。これらを混ぜたものを型で焼き、できあがった「とうろう」を同じ型同士、紙製の紐をつけ貼り合わせたて完成です。

サトウ商事 佐藤社長
「うちの会社は、日本の文化というものを大事にしていきたいということでやってますので、これも地元のもの、青森のものなので、きちんと残していきたいと思っています」

その色合いと形から、思わず「カワイイ」と言ってしまいそうになるモナカのようなモノは、「とうろう」と呼ばれるお盆用品だったことがわかりました。
北海道、東北の一部で受け継がれてきた「とうろう」。機会があったら一度手にとってみてください。

青森テレビ「わっち!!」月~金 16時25分放送(2019年8月15日放送回)