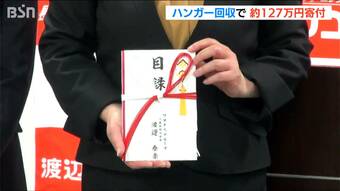2023年の夏、記録的な猛暑とそれに伴う渇水に見舞われた『コメ王国 新潟』は、主力品種のコシヒカリをはじめ各銘柄米で等級、作況ともに低下が見込まれ、近年にない逆境に立たされています。
ここ半世紀の新潟のコメ作りを振り返り、今後の稲作農業を考えます。
戦中・戦後の土地改良で日本一の“美田”が誕生
信濃川や阿賀野川という、国内有数の大河が流れる「越後平野」。
大河川によって形成されたこの沖積平野には江戸の時代から広大な湿原地帯が形成され、現代とは異なり胸まで水に浸かって田植えをしなければならないほか、大規模な河川の氾濫も発生するなど、およそ稲作には適さない時代が長く続きました。
その後、明治・大正・昭和の時代に入って、大河津分水路などの掘削や大規模な排水機場の完成などにより、水田の土地改良が劇的に進みます。

1948年(昭和23年)には新潟市に、当時“東洋一”といわれた『栗ノ木排水機場』が完成。かつて泥沼だった水田が乾田に生まれ変わったのは、その象徴的な出来事となります。
300年の長きに渡り、10万haの『沼』を人の手のみで「農地」に変えてきたのが、この越後平野の“歴史”なのです。