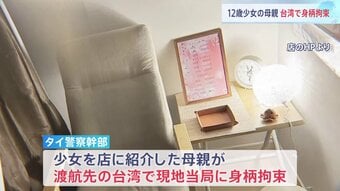東西で違う?「線香花火」
手持ち花火の〆は、やっぱり線香花火。
実は線香花火、‟東西で違う”ということをご存じですか?
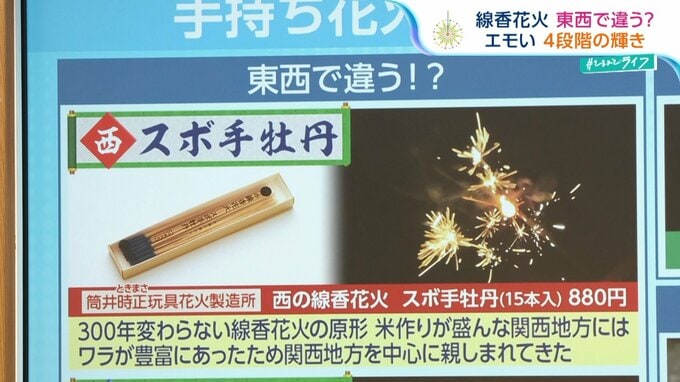
西の線香花火として古くからあるのが、「スボ手牡丹」。
現在は福岡にある筒井時正玩具花火製造所で製作されています。
300年変わらない線香花火の原型で、持ち手がワラで出来ています。米作りが盛んな関西地方にはワラが豊富にあったため、関西地方を中心に親しまれてきました。
こちら、持ち方に特徴が。
火がついている方を斜め上に向けて持ちます。
火が消えかけたら、フーっと息を吹きかけると勢いが増し、美しい火花を散らします。
風を好むため、風量を調節しながら遊べるタイプの珍しい線香花火です。
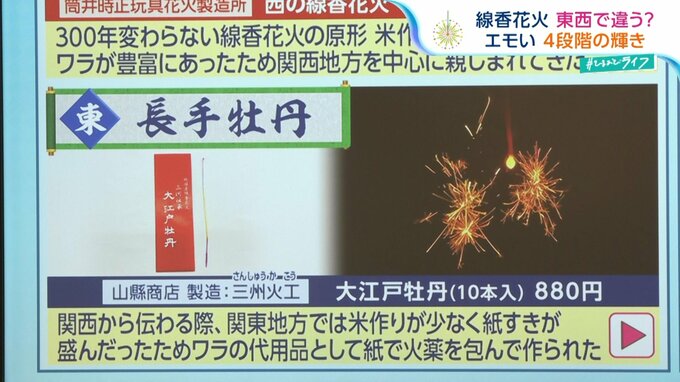
東の線香花火として知られるのは、現在主流となっている「長手牡丹」。
『大江戸牡丹』〔山縣商店・三州火工〕などがあります。
関西から伝わる際、関東地方では米作りが少なく紙すきが盛んだったため、ワラの代用品として紙で火薬を包んで作られました。
「もう落としたくない…」線香花火を長持ちさせる方法

線香花火は4段階で変化するのが特徴です。
点火から次第に大きくなっていく火の玉・・・「蕾」
パチパチと力強い火花がはじけ始める・・・「牡丹」
勢いを増し次々に火花が散る・・・「松葉」
火の玉がだんだんと光を失い散っていく・・・「散り菊」
恵俊彰:
「蕾」の時に落としたら本当にショックですよね…

線香花火を長持ちさせるコツを長谷川さんに聞きました。
▼先端のくびれた部分を、軽くねじる
▼垂直ではなく斜め45度に傾けて持つ
国産の線香花火を使って比較したところ、このワザで21秒も長持ちしました。
(垂直:平均46.193秒 ねじって斜め45度:平均67.162秒)
恵俊彰:
落ちるのが嫌だからまっすぐにしてたよ。