保育の現場は、ここ数年で変わってきていると専門家は見ていて、保育士にはそれぞれの子どもに対応するスキルがより求められていると指摘します。
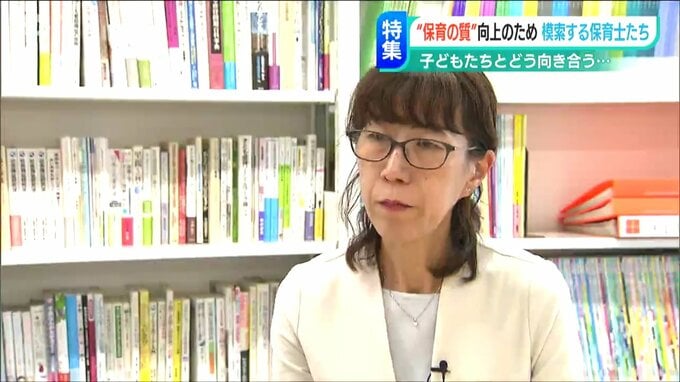
【新潟県立大 小池由佳教授】
「集団になじまない子どもが増えている。個であったりとか2、3人のグループだったり、あるいはもうちょっと大きな集団だったりという中で、子どもを育てていくというようなものが、今求められるようになってきている保育現場だと、今までのスキルと違うんですよ。個別対応になればなるほど子どもの見立てる力とか、そこでこの子が何を遊べているのかなという力がいるというところの、過渡期じゃないけど難しさがある」

この日、みのりこどもえんで開催されたイベント「保育cafe」。月に1回新潟市内外の保育士が集まり勉強するものです。
【おもちゃコンサルタントマスター 岡田真弓さん】
「保育の現場の中で先生方がこういったおもちゃをどんなふうに形で使っていったら保育環境に役立てるかな」

今年4月から始まり、今回が3回目。この日のテーマは「おもちゃ」です。保育士自ら、おもちゃで遊びながら、その目的や遊びのバリエーションなどを学びます。
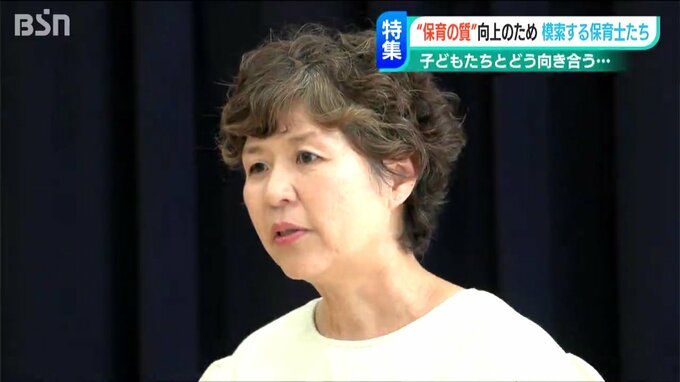
【おもちゃコンサルタントマスター 岡田真弓さん】
「さっきもちょっと崩しちゃったお友達がいたんだけど、『ああ仕方ないな』とか『やりなおそうか』って、それって子どもたちの中にもよくあることですよね。崩れちゃって泣く子もいるけれども、じゃあどうしよう、もう一回やろうっていうふうに、子どもたちが自分たちで問題を解決していく力にもなる」

保育cafeを始めたのはそもそも、保育士のスキルアップが目的でした。外部から人を呼ぶことで、園内の研修では得られない知識を学び、様々な園の保育士と交流して悩みを共有します。
【保育士】
「他の園の先生方の話を聞いて自分の保育ってどうかなと見直すきっかけになった」
「実際に遊んでみて楽しさとかも教えたりとか、おもちゃの特性とかも知れたのでそれを子どもたちにも伝えていけたらなと思った」
イベントはSNSで発信し、新潟市以外の保育士も参加するなど広がりを見せています。

【みのりこどもえん 梅川一美園長】
「子守りだったら、けがさえさせなければいいけど、私たちは集団の保育施設であってプロなので、やっぱり子どもに刺激を与えてあげたいし、楽しいことも提供してあげたいし、一緒にその時間を共有したい。私たちが知ることで保育も楽しくなるし、子どもたちも楽しいし、そういう保育ができたらいいなと思っている」
不適切保育が多く報じられる中、より良い保育のあり方を子どもたちと向き合いながら模索を続けています。
“不適切な保育”ということが大きく報じられる中、新潟市の多くの保育士がこのように「保育」と向き合って努力を続けています。不適切な保育を防ぐためには保育施設が大人が働くための「預かりの場」ということだけではなく、子どもたちの成長や発達を守っていく大事な場所であるということを、私たちもしっかりと認識して社会の中で認められることも重要だと専門家は話していました。














