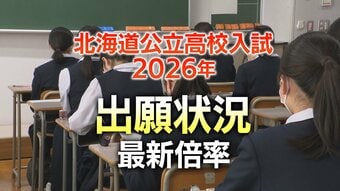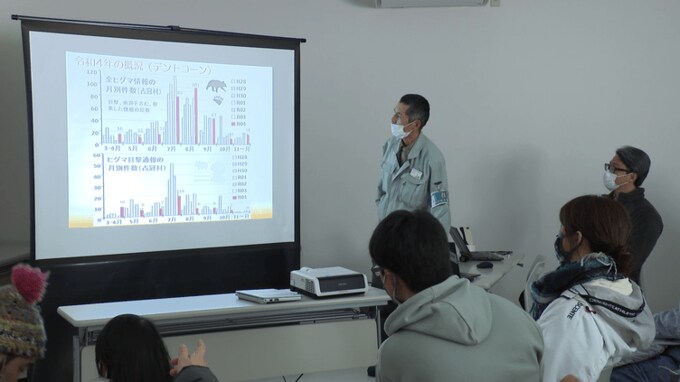
ただ、「専門員だけにすべてを任せない」ことが、占冠村のさらにすごいところです。
有光さんは、「自分にできること」について話していました。
「クマがいることについては、山が健全というか自然が豊かな状況だと思う。家畜を飼う立場だと襲われるリスクはあるけど、クマを含めた野生獣のことを、正しく知って正しく恐れるのが、できることかなと」
クマを引き寄せるものを置かないのはもちろん、見回りを強化したり、JRなどとの事故で傷ついたシカに気がついたら、クマがシカを目当てにやってくる前にJRに相談したり、浦田さんに情報共有したりと、自分にできる安全対策に取り組んでいます。
「トマムシープファーム」は、浦田さんがいる役場から、車で30分ほど離れた距離にあります。
「浦田さんもたくさんの仕事を抱えているのを知っているので、すぐには動けないときもあるかもしれない。離れた場所にハンターとして自分がいるので、そこは役に立ちたい」

クマの駆除について、道内外から、各地域に批判の声が寄せられることがあります。
道内の複数のハンターから、駆除の判断をしたのが行政でも、ハンターが直接批判されることもあると聞きました。
取材している私自身も、子どもの頃から動物好きで、記者になるまでは単に「クマを駆除するのはかわいそう」と思っていました。
けれど、有光さんのように「駆除以外の選択肢も含めて、その都度一番いい対応を考えよう」としているハンターの存在を知ると、動物と向き合うということは、単に「命を奪わない」ということではないのかもしれないと、気づかされます。
生きるために動物の命を食べるとき、「いただきます」と言うことに、通じるものがあるのかもしれません。

ヒツジやクマ、シカなど、動物の命に直接向き合う機会が多い有光さん。
いま、全道で野生動物と人との距離が近づいている中で、住民はどんな心持ちでいたらいいと思うかを尋ねると、少し考えて、「地域によって違うと思う」と答えました。
「子どもの通学路にクマが出たという人や、庭の作物を食べられたという人に、占冠村と同じ考え方でいろとは思わないし、『クマは当たり前にいるから怖がらない』というのも、違うと思う。正しく怖がるために、地域として情報を集めて対応策を考えられるようになればいいのかなと思います」
対応策を考える主語が、「地域」だった有光さん。
浦田さんのいる意味を語りながらも、自身もハンターとして・いち住民としてできることをしようとする姿に、「野生鳥獣専門員」というポストだけでなく、専門員と地域の人たちが「目指したい地域の姿」を共有して、協力することが重要だと感じました。

※掲載の情報は取材時(2023年2〜3月)の情報に基づきます。