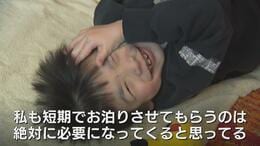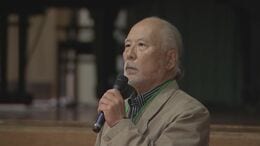車を利用する機会が増えるこの時期、気を付けなければならないのがシートベルトの着用です。特に後部座席について、大分県内の着用率は3割程度と全国ワースト5位です。なぜ徹底されないのか? 現状と着用率アップの取り組みを取材しました。
交通事故を再現した実験映像では衝突直後、衝撃でシートベルトを付けていない後部座席の同乗者が前方に飛び出します。
15年前、2008年の道交法が改正され、後部座席のシートベルトの着用は一般道、高速問わず義務化されました。一方で着用率は低迷しています。
警察庁とJAFの調査によりますと、一般道での全国平均は4割程度にとどまり、さらに県内の着用率は30・7%で全国ワースト5位です。
なぜ徹底されないのか!?
(県警交通企画課・田口哲浩次席)「明確な理由はわからないのですが、ちょっとしかない距離だから大丈夫だと思っている方もいるのではないか。シートベルトをしていないと衝突の衝撃で車外放出の危険性も出てくる。運転手にもぶつかって、それでまた重大な事故を引き起こす可能性もある」
県警によりますと、過去5年間県内で発生した交通事故で、後部座席に乗り亡くなった人と重症者の6割以上がシートベルトをしていませんでした。
後部座席のシートベルトについて、まちで聞いてみると…
(街頭で)「シートベルトが(着用の際)窮屈に感じるところがある。自分の車なら(差込口が)ここだというのはわかるけど、友達の車に乗せてもらった時はわかりづらいと思います」
こうした声に対し、JAF大分支部では、「少しの工夫で改善するのでは」と指摘。
まず、「引き出しが窮屈」、「差込口がわかりにくい」といった意見については…。座席に浅く座ったうえで、ベルトを引き出し、上半身を内側にひねって金具を差し込むとスムーズに着けることができるということです。
(吉田キャスター)「体をひねることで差込口をしっかり見ることが出来ます。シートベルトもスムーズに動いて着けやすいですね」
さらにJAFオリジナルのユニークなアイテムが…
(JAF大分支部・岩元幹太さん)「座った際に自分のベルトの金具の位置とバックルの位置がわかりづらく、どちらにつけていいのか迷う方もいます。そんな時はこちらシートベルト用の蓄光シートというものです」
差し込み口と金具をみつけやすくなるシール。また、差込口がシートに埋もれている場合は、市販のリストバンドの活用をすすめています。
車で出かける機会の増えるこの時期、ドライバーも、同乗者も、後部座席のシートベルトを常に意識することが着用率アップの第一歩といえます。