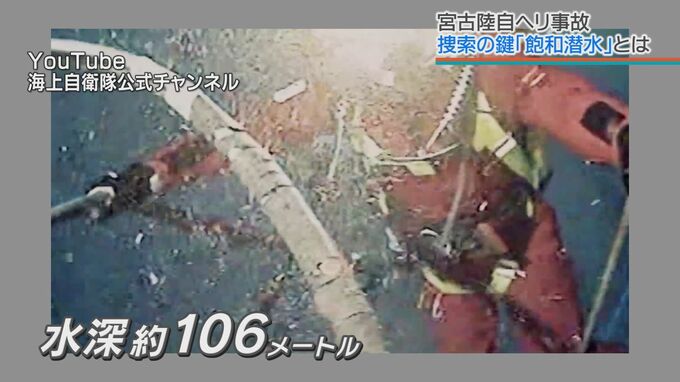竹内記者「午前11時前です。潜水艦救難艦ちはやが、時計回りに回転して、船上で隊員が作業する様子が見られます」
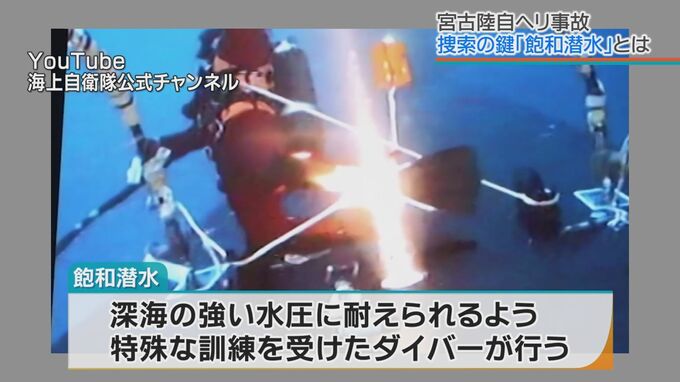
捜索現場で繰り返し行われている『飽和潜水』。飽和潜水とは深い海の強い水圧に耐えながら作業を行えるよう特殊な訓練を受けたダイバーが行う潜水方法です。
気圧状態を潜る深さの水圧と同じにしたカプセルで体を慣らした後に、海中での作業が行われます。
今回機体や隊員とみられる5人が見つかったのはおよそ106mの海底で、潜水士による引き揚げ作業が進められていますが、今回の捜索現場は急激に深さが変わる不規則な地形です。

周辺の海底地形を表した図をみても、機体が発見された水深およそ100mの地点から数百メートル。沖に進むと、150m、200mと急激に深さが増していることが分かります。
水難学会 安倍淳理事「アメリカのグランドキャニオンのような凹凸、山あり谷ありのようなところにあると思うので、回収する飽和潜水士の作業の難易度も高いもの」
元海上自衛隊員で、海難救助に詳しい安倍さんによると、潜水士の作業を阻んでいるのが、この伊良部島沖の海底地形だといいます。

さらに潜水士による作業は、一度に加圧ホースが届く半径およそ30m程度の作業しかできず、少しずつ船の位置を変えながら地道な作業が行われています。
水難学会 安倍淳理事「今まで発見された漂流物の形をみると、かなり破損が激しいということで、おそらく本体もかなりの変形が予想されます。中に搭乗されていた方が挟まれていたりして揚収できないことになっているかと」

損壊がかなり激しいとされている機体の状態によっては、この先のサルベージ船による引き揚げも難航を極めることが予想されます。
水難学会 安倍淳理事「いま多分潜水士が入って、傷みがあるのか、例えば重要な部分をつり上げるにしても、人間でいう背骨のような部分が傷んでいるのかいないのか、これによっては機体の揚げ方、揚収の仕方も変わってくる」

引き揚げ作業と併せて現場では原因究明の鍵となるブラックボックスの捜索も進められています。
水難学会 安倍淳理事「交信があってからレーダーロストするまでの2分間、『空白の2分間』ということがよく言われているので、その間に急激な事象の変化が起きたと。中に乗っている人が必死に立て直そうとしても立てなせないような急激な事象が起きたと思う。事故の原因を究明するために一番大事なボイスレコーダーや機体の状況、エンジン、ギアボックス、テールローター含めた機体の尾部の部分を慎重に捜索しながら回収するという作業になっていく」

この「空白の2分間」に何がったのか。まだ見つかっていない5人の捜索とともに、事故原因の解明に向けた回収作業も今後の焦点となります。