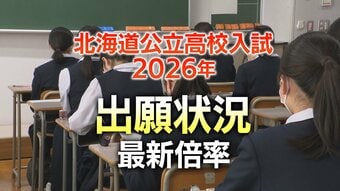HBC報道部・山﨑裕侍監督のコメント
テレビと映画はこうも違うのか…。
年の瀬も押し迫り、HBCの社内も閑散とした去年12月下旬。編集室に一人こもり、素材を1カット1カットを見ながら編集していて、驚きました。
テレビは「わかりやすさ」を求めます。特に夕方のテレビ番組はナレーションや字幕、音楽などを「足し算」していきます。少しでもわかりにくい場面があれば、視聴者がチャンネルを替えてしまうからです。一方、映画は説明しすぎることはむしろ逆効果です。ナレーションや字幕は少なくして、映像と音声の力を信じ、見ている人に感じ方を委ねます。いわば「引き算」の世界です。

道警ヤジ排除問題は、選挙の演説会場でヤジを飛ばしたり、プラカードを掲げたりしようとした市民を警察が排除した表現の自由をめぐる問題です。テレビの特集やドキュメンタリー番組では、法律のどの部分が問題なのかを専門家にインタビューしたほか、警察の説明を検証して矛盾点を指摘しました。
しかし映画用に編集しなおすために、当事者の表情やインタビューを一から見直すと、放送とは違った世界が画面から立ち上がってきました。
例えば排除の映像。最初は衝撃でした。「まるでロシアや中国のようだ」。しかし警察の矛盾ばかりの説明と合わせてみると喜劇のように思えてきます。そして垣間見える背後の闇を感じると、恐怖を覚えます。
例えば桃井希生さん。映画では彼女の吃音と「生きる価値がない」と思っていた人生がいかに変化していったかを掘り下げました。あの日彼女は警察に排除されたけど、彼女自身は決して敗れてはいません。丹念に追うと、桃井さんの成長物語でもあります。
例えばジャズ。予告編でもつかっていますが、今回の作品の音楽は全編ジャズを使っています。それは桃井さんがふともらした「世の中にはノイズが必要」という言葉。ジャズはトランペットやピアノ、ドラムなど多様な楽器が即興によって個性を出しながらも調和する音楽です。ノイジーは自由であり、主張です。試しに導入部分に音楽を当ててみると驚くほどシーンに合いました。