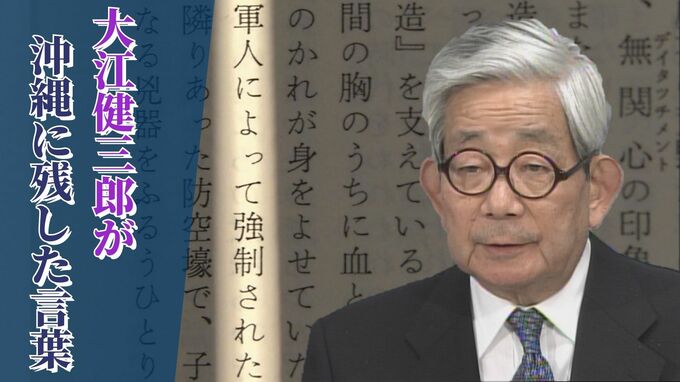今月3日、88歳で亡くなったノーベル賞作家の大江健三郎(おおえ けんざぶろう)さん。『沖縄ノート』を執筆し、戦後の日本のあり方を問い続けてきました。沖縄への思いが綴られた大江さんの『言葉』を振り返ります。大江健三郎さん。戦後の日本を代表する文学者は、創作活動を通して沖縄を見つめてきました。

大江健三郎さん(1992年放送)「きょうは小説家としてどのように沖縄から学んできたか、それを自分の文学の方向でどのように生かそうとしてきたか、それから今どうしているかお話したいと思っています」
1992年に放送された、RBCの番組「大江健三郎沖縄を語る」の中で、沖縄への思いをこう表現していました。
大江さん「20年前(1972年)に視点を置きまして、自分が20年前に沖縄全体から何を読み取ろうとしたのかもう1回見てみたい。一旦小説家になって、30歳くらいになっている人間が、どのように自分の小説を作り直すか、そういうことを考えるときに、沖縄で経験したことが有用・大切だったという風に思うわけです」

復帰前の沖縄を訪れた大江さんが1970年に出版した『沖縄ノート』。
沖縄戦当時に慶良間諸島で起きた“集団自決”の記載をめぐって訴えられると、法廷では一貫して「軍命はあった」と主張。
2011年に最高裁で勝訴が確定するまで、歴史の歪曲を許さない姿勢を貫きました。
大江さん(08年 1審判決後)「軍の強制があった、そしてああいう結果が起こったと考えている。私の書物が主張していることはきょうの裁判でよく読み取って頂いた」
護憲運動にも携わり、2004年に『9条の会』の設立に参加。
名護市辺野古を訪れた際には、移設工事に反対して座り込みを続ける人々を激励、「国が相手でも諦めなければ勝つという市民運動に共感する」と伝えました。
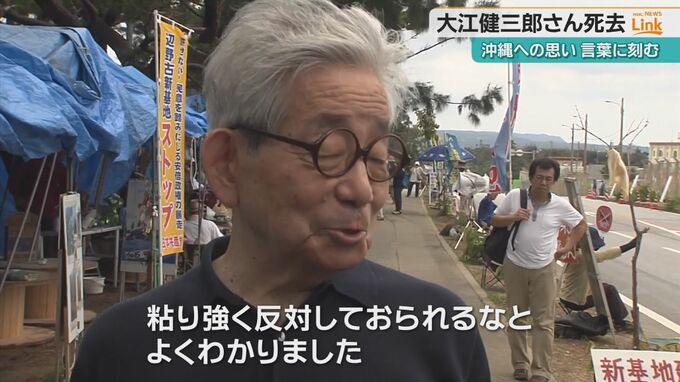
大江さん「市民の人たちが本当に市民らしく、粘り強く反対しておられるなということがよくわかりました」
沖縄で定宿にしていた沖縄第一ホテルには、大江さん直筆の色紙が飾られています。
沖縄第一ホテル オーナーの娘・渡辺克江さん「私が学生のころに『先生どうしてこんな大きい眼鏡かけているんですか?』と聞いたところにこにこっと優しく笑ってくださって『僕はねハンサムじゃないからこういう眼鏡をかけているんだよ』って言った笑顔が忘れられません。優しい笑顔でまたこの門から入ってきてくださるんじゃないかなという思いがあってまだ現実を受け止められません」

沖縄第一ホテル 島袋芳子オーナー「出会えてありがとうございましたって伝えたい。こうやってお話もできるということは、何かのご縁があったなと思って本当にいい人に出会えて良かったなって思いますね」
沖縄の戦後の姿を通して、日本の民主主義のあり方を問うた大江さん。60年あまり、言葉で戦い続けた生涯でした。
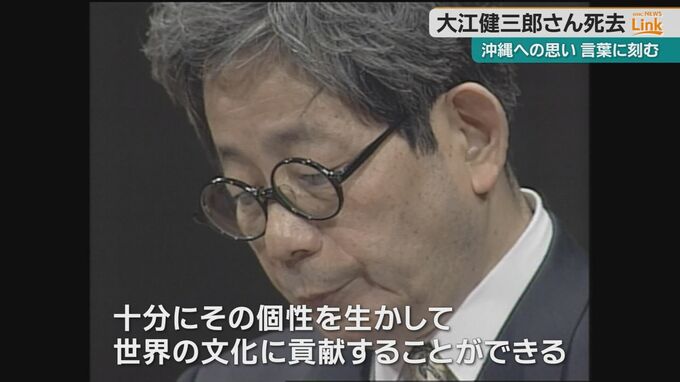
大江さん「地球上で帝国主義が終わりを告げるとき、沖縄人は苦世から開放されて甘世を楽しみ、十分にその個性を生かして世界の文化に貢献することができる」