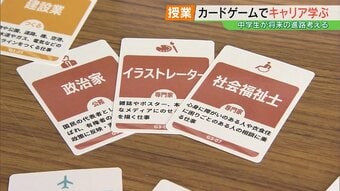東日本大震災、東京電力福島第一原発事故から12年となった3月11日、避難区域の復興や処理水の海への放出など様々な課題を抱える中、それぞれが震災から13年目へと一歩を踏み出しました。
福島県内では、震災による死者は関連死を含めて3935人、今も224人の行方が分かっていません。
浪江町の霊園では、震災で亡くなった人を思い、線香や花をたむける人の姿が見られました。
親戚を亡くした女性「昔の素敵な町になっていくことを望んでお祈りしていました」
空高くに掲げられた、2023羽の折り鶴。
福島第一原発が立地し、原発事故で一時全町避難となった大熊町では「復興のつどい」が行われました。

会場には、町民をはじめ、4月から町内に戻る義務教育学校「学び舎 ゆめの森」の子どもたちも集まり、羽にメッセージを書いた折り鶴を飾りました。
学び舎ゆめの森・後藤愛琉さん「大熊がにぎやかな町になってほしい思いで書きました」
学び舎ゆめの森・齋藤羽菜さん「平和を願ってとか、亡くなられた方々がどうか安らかにという思いでつりさげました」
3・11おおくまのつどい実行有志の会 松永秀篤代表「今までの思いがみんな表れているのかなと思った。忘れてほしくないなというのが一番根っこにあって」
折り鶴には、戦火に見舞われているウクライナや地震で被災したトルコの国旗をイメージしたものも…。
「復興」や「平和」が願いです。
県主催の追悼式は、岸田総理が参列して行われ、津波で両親を亡くした遺族の男性が、追悼のことばを述べました。
遺族代表・宮口公一さん「とても悔しく残念です。その気持ちは12年たった今でも全く変わっていません。この震災の教訓を活かし、決して忘れないようにしていかなければなりません。」
終了後、岸田総理は海への放出時期が迫る福島第一原発の処理水について、地元の理解を得ることを強調しました。
岸田総理「漁業者をはじめ、地元の方々の懸念に耳を傾け、政府をあげて丁寧な説明と意見交換を重ねてまいります」
原発周辺にある「帰還困難区域」では避難指示が一部で解除されましたが、いまも2万7000人あまりが県内外に避難していて、課題は山積しています。