東短リサーチ社長 加藤出氏:
おっしゃる通りです。これだけ買うともう流通する国債がほとんどないという状況にもなってきて、財政法第5条が禁じている日銀の国債引き受けと実態上は何も変わらないというか、とにかく日銀が国債を市場から買いまくって金利の上昇を抑え込んでいると。なぜ上限が0.5なのかという経済合理性については何の説明もなく、単にもうやめるにやめられないから猛然と国債を買っているというだけなので。
――直近で金利が跳ねると春闘にも影響があるし、株安も招くので好ましくないことはないのだろうが、こうして見てくると異次元緩和は当初必要だったものがいろいろな形で修正を迫られている。客観情勢も変わってきているということなのか。
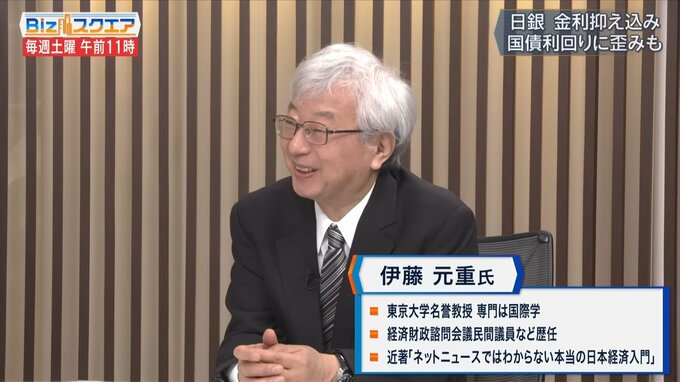
東京大学名誉教授 伊藤元重氏:
昔は一生懸命国債を買っても物価が動かなかった。今何が起こっているかというと物価が上がって、金利を下げるために国債を買わざるを得ない。状況が逆転してしまっている。明らかに金融政策が賞味期限切れというか次のステージに行かなければいけないのですが、これまでやった政策があまりにも大規模だったために市場に対する影響とか非常に注意深くやらなければいけないと。これが今、日本銀行が突きつけられている問題だと思います。
日銀総裁交代後の政策変更は?

日銀が発表した物価の見通しは、22年度は3.0%と目標の2%を超える。23年度は1.6に落ちて、24年度は1.8となっている。
――23年度の物価見通し1.6%はずいぶん低いと思ったが、どういう背景か。
東短リサーチ社長 加藤出氏:
ここは意図的に低くしたのだろうなと思います。日銀のインフレ目標は2です。実際は2を超えても不思議はない状況だと思うのですが、例えば1.8ぐらいに上方修正すると、22年7月は1.4、10月が1.6、23年1月がもし1.8となると、今度の4月は2に乗ると市場は思うわけです。そうすると次の総裁のデビュー戦である4月の会合で、今の枠組みを変えるのではないかという思惑も出やすいでしょうから、そうすると次の総裁が大変なことにもなるので、フリーハンドを持ってもらうというためにも意識的に低めに出して、かつ1.6であれば今この瞬間に黒田体制のもとでも変える必要はないのだという印象も出したいと。
――今の物価の上昇はコストプッシュ型で一時的だから変えなくていいという論理を補強するような数字が出てきているということだ。例えば23年度も24年度も2.0という数字が出てくれば、2%目標を3年連続で達成しているのだから枠組み変更という話になる。
東短リサーチ社長 加藤出氏:
黒田総裁は2%インフレを目指していたので、そういうストーリーにして政策を変えて退任するという手もあったのでしょうが、修正するのが大変難しい政策なので、在任中は触らないで終わろうというシナリオで、多分22年から来ていたのでしょう。無理矢理シナリオを維持するため、出口に行かないということを維持するためにこういう説明になっているのでしょう。
――伊藤氏は安倍政権時代に経済財政諮問会議にもいてデフレ対処に苦労してきた。今の日本の水準はデフレではない、あるいは目標をほとんど達成したと言っていいと見ているか。
東京大学名誉教授 伊藤元重氏:
来年どういう予想かという問題ですが、おそらく2%を超えるだろうと考えている人が多いと思います。そうするとやはり完全にステージは違うと思いますから、金融政策の領域であれば正常化に行かざるを得ないだろうと。もう一つアベノミクスの反省点は、金融では需要は喚起したのですが、実際のサプライサイドで成長率が上がらなかったのです。要するに民間の投資が非常に弱かったので、そこはどう変えたらいいか。今グリーンやデジタルという政策で言われているのは民間投資をどう引っ張ってくるかと。政策の重点がかなり変わってきていることは事実で、金融政策についてのキーワードはいかにスムーズに素早く正常化するかということだと思います。
――これまではデフレ傾向の中で世界中が金融緩和に走って金融政策に重きを置いた政策を取ってきた。インフレ時代になると局面が変わり、金融より財政にシフトということか。
東京大学名誉教授 伊藤元重氏:
キーワードですとポリシーミックスということでしょうか。政策をどう使い分けるかと。金融重視でやってきたのがこの5年10年だったのですが、時代が変わってきたということだろうと思います。いかに民間投資をうまく動かすような政策をやるかということが問われていると思います。
――春には日銀の総裁も変わる。変わった後の政策変更に向けた手順はどう考えたらいいか。
東短リサーチ社長 加藤出氏:
今やっている10年国債の金利を固定するというのはあまりに無理があって、世界中どこもやっていません。これを金利はマーケットが決めるという世界に戻るという作業を4月から6月の間に次の総裁はやらざるを得ないのではないかなと思います。ただ、金利が跳ね上がると多方面に問題が出るので、金利の固定はやめるが、今後も日銀は数十兆円ぐらい国債を買っていくと言って安心感を市場に与えつつと。長期金利がある程度落ち着いてくれば、日本の銀行や保険会社は資金運用難なので、国債の金利がある程度上がったら買い始めるとは思うのですが。ある程度落ち着いたら今度はマイナス金利政策というのを解除すると。ただ解除してもせいぜいゼロ金利に戻るぐらいの話でしょうから、そんなに急激な金利上昇にはなりにくいと思います。
異次元の金融緩和からの脱却という重い課題は、後任の総裁に引き継がれることになりそうだ。
(BS-TBS『Bizスクエア』 1月21日放送より)














