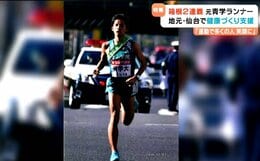犯罪が成立するには、被告人が行った行為が「構成要件」を満たしていなくてはなりません。田口被告が行った行為が、構成要件に該当しなければ罪には当たらない、つまり無罪となるのです。
田口被告が問われている電子計算機使用詐欺罪を簡単にみると・・・
正当な権限がないのに電子計算機(パソコンやスマホ)に、ウソの情報や不正な指令を与え、不法に利益を得た者は、10年以下の懲役に処すると規定されています。田口被告が行った行為が、この罪あたるかどうか、検察側と弁護側で主張が分かれているのです。

論告から検察側の主張をみると、誤って振り込まれた金は本来は返すべきであり、ネットカジノという法令や公序良俗に違反する目的で振り込んだことも踏まえると、田口被告が振込をする正当な権限がなかったとしました。「インターネットバンキングに入力された情報一つ一つにウソはない」と弁護側は主張しますが、正当な権限があるように装ったことは、電子計算機にウソの情報を与えることになり、罪は成立するとしました。
その上で、約4630万円の公金が海外のネットカジノに流れた結果は重大。金が返還されたのは町の代理人弁護士がとった措置がきっかけで、田口被告の努力や反省の態度とは全く無関係だとしました。田口被告が「町職員の対応に対するストレスや、どうすればよいかわからない不安から犯行に及んだ」としたことについては、「町職員の対応は真摯なものだった。残高を確認した後は、不安はむしろ解消されたはずだ」と指摘。町への返金など後先を考えず、すぐデビット決済の限度額を引き上げ、34回にわたって多いときには400万円を使うなど、自分の金では決して行わないような振り込みを自分の預金のように繰り返したあげくカジノで使った大胆で悪質な犯行とし、懲役4年6か月を求刑しました。