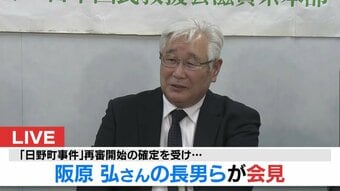いつから「君(くん)呼び」?背景には身分制度を崩したい思いか
井上キャスター:
「くん」はどこから来たのでしょうか。調べてみると「吉田松陰」の名前が出てきました。
吉田松陰といえば、松下村塾が有名です。これまでの教育を変えていこうということで、教科書や月払いの金額もいらず、個性を大事にしました。

歴史作家の山村竜也さんによりますと、当時は身分制度が色濃く残っていましたので、身分がバラバラな人が集まると、どうしてもお互いに気を遣ってしまいます。なお、この時、目下の人には「殿」、目上の人には「様」を使用していました。

個性を重視する「松下村塾」としては、この身分制度を何とか崩したいということで、吉田松陰が言い出したのが「くん」です。
「“主君”からとって、身分関係なくお互いに「君(くん)」を付けたらどうかということで、画期的な呼び方を導入しました。
ゆくゆく松下村塾出身の伊藤博文氏が初代総理大臣になったとき、国会で「くん」付けを使ったことで広まっていきました。
社会的にも教科書に「くん」付けが載ったり、夏目漱石の「坊ちゃん」で「くん」付けが入ったりして、社会に広がっていったということです。
時代背景を考えて、対等にしゃべるための「くん」付けであったら使っていいのではないかというご意見もあるでしょう。
はたまた、今の学校教育を考えると、「くん」付けやめましょう、男女の付き合いをやめましょう、「さん」付けをしようとなっているのに、時代に遅れてるのではないかというご意見もあると思います。

青木さやかさん:
子どもたちは男女どちらとも「さん」付けで呼びましょうとなっていますね。
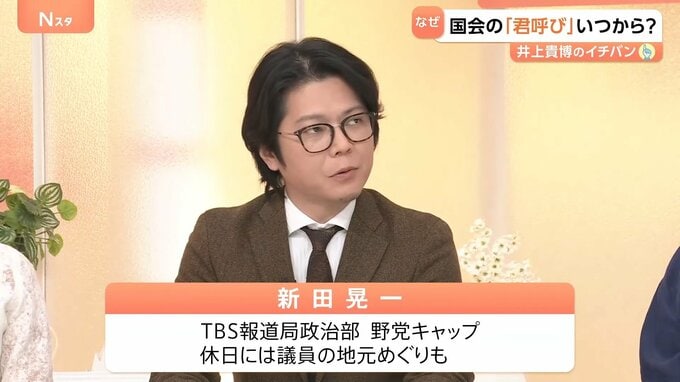
TBS報道局 政治部 新田晃一 記者:
時代とともに国会も変化していかなければならないのだろうと思っていて、おそらく枝野氏もそう思ったのだろうなと思います。
「さん」付け、「くん」付けなのですが、社会党・土井たか子氏が議長をやっていたときに、本会議で「さん」付けを始めてみたり、自民党・野田聖子氏が女性初の予算委員長になったときも、「さん」という呼び方を始めていました。
野田聖子氏ご本人にもお伺いしましたが「普通の生活をしていて、女性に『くん』とは言わないでしょ」とおっしゃっていて、そうだなと思いました。

出水麻衣キャスター:
国会の論戦はオープンになっていて、国民の皆さんも見るわけですから、何か余計なところで違和感を抱かせるくらいだったら、時代とともに変化してもいいのかなと思います。
井上キャスター:
今SNSなどで、ある意味、監視されている中で、「これはどうなのだろうか」と、良い方向に変わっていくと良いなと思います。