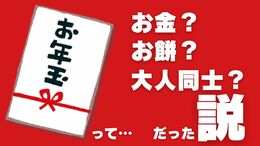新潟県内でも被害が相次ぐクマですが、秋になり子グマの目撃が増えています。なぜ子グマが人里にでるのでしょうか。専門家に聞くとクマの生態とエサの関係が見えてきました。
【新潟大学 箕口秀夫 名誉教授】「人身事故がこんなに多く発生するというのは予想外」

森林生態の専門家でクマにも詳しい新潟大学の箕口秀夫 名誉教授が予想外と話す今シーズンのクマ。県内ではすでに16人のけが人が出ています。

先月31日には阿賀野市の建設会社でクマ1頭が立てこもったほか、

村上市で撮影された写真には民家の近くを歩くクマの姿も。いずれも体長50センチほどの子グマと見られています。

実は、警察などが発表するクマの目撃情報も今年は子グマが多くなっています。箕口 名誉教授は餌となるブナの実のつき方とクマの個体数の関係を指摘します。
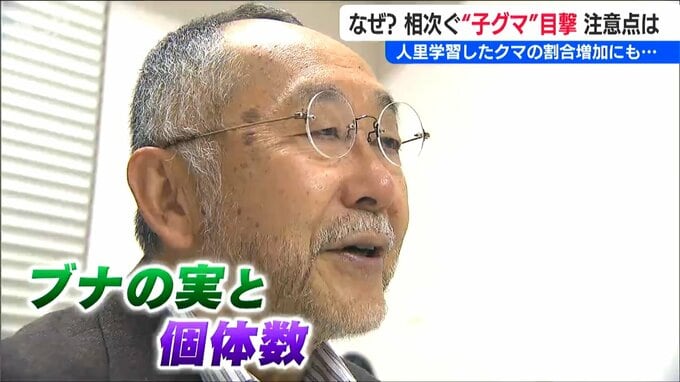
【新潟大学 箕口秀夫 名誉教授】「子どもを連れたお母さんクマがたくさん活動をしている年っていうのはブナが凶作になる」今年、県内のブナは『凶作』。過去15年間で最も実がつかない年になっています。

箕口教授によりますと、豊作の年にクマは多く子どもを生みますが、その翌年以降ブナなどは凶作が続く傾向にあるということです。

つまり、子グマが多いにも拘わらず山に食べ物がなく人里に下りてきていると考えられるということです。

さらに…
【新潟大学 箕口秀夫 名誉教授】「その子熊がお母さんグマになると、自分の子どもにそのことを今度は教えるっていうことになりますので、どんどんクマの集団の中に人里や市街地のことを学習したクマの割合が高くなっていくっていうことは考えられる」
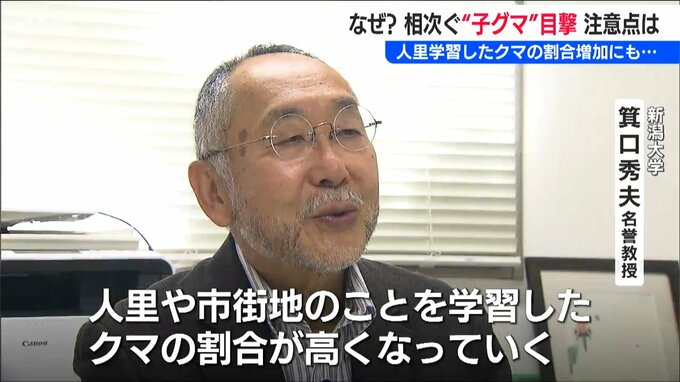
市街地に出る子グマは母グマが箱ワナなどで捕まり単独で徘徊している可能性もあるということですが、子グマの近くには母グマがいることを忘れてはいけません。

【新潟大学 箕口秀夫 名誉教授】「子持ちの母グマは他のクマに比べて神経質になっています。母グマの方がそこに近づいたものに対して防御の意味で攻撃を加えるといったようなことが当然起きます」
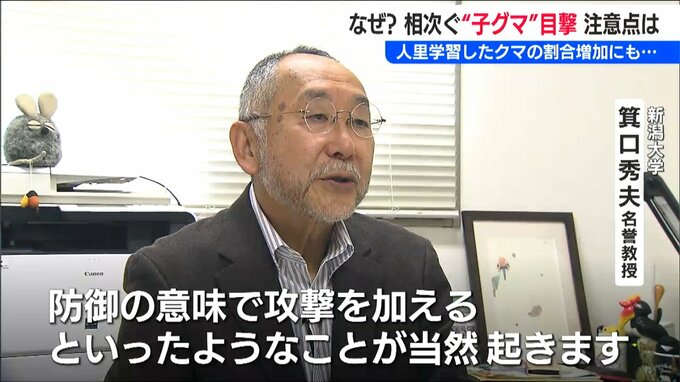
人里に下りてくるクマは食べものがあると、冬眠しない場合もあるということで今後も警戒が必要です。