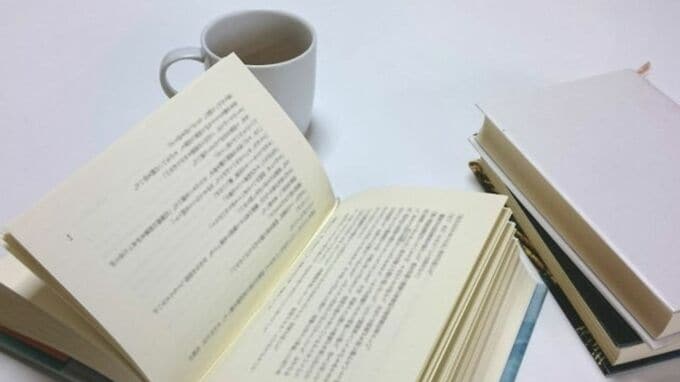酷暑をようやく乗り越えて、涼しい朝を迎える日も増え、「読書の秋」という感じになってきました。「さて、どんな本を読もうか」と選ぶ際に芥川賞など文学賞の受賞作を読んでみようという人は少なくないと思います。ところが、いまこのあたりに「異変」が起きています。10月3日放送のRKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演した毎日新聞出版社長の山本修司さんがコメントしました。
「該当作なし」から生まれた「本屋大賞」
ことし7月16日、27年ぶりに芥川賞・直木賞で「該当作なし」となったことは記憶に新しいところです。書店からは、販売のチャンスがなくなったと悲鳴が上がりましたが、その衝撃の発表を受けて「賞がないなら勝手に作っちゃえ」という動きが出ました。「かってに芥川賞・直木賞」というものですが、私は少し驚くとともに、そこに「たくましさ」を感じました。
ただ、これに似た話は以前にもありました。例えば2002年の第128回直木賞。候補作は横山秀夫さんの『半落ち』、京極夏彦さんの『覘(のぞ)き小平次』、石田衣良さんの『骨音』、角田光代さんの『空中庭園』など、そうそうたる作家、作品が並び、文学ファンも書店も固唾をのんで見守りました。
それなのにまさかの「該当作なし」。それで不満を持った書店員たちが「作家や出版社の関係者を入れずに、自分たち店員が選考する賞をつくろう」ということで2004年に創設されたのが、今ではすっかりおなじみとなった「本屋大賞」です。芥川賞・直木賞に迫ろうかという存在感を持つこの賞は、「該当作なし」から生まれたのです。