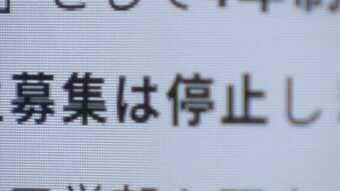「手をつけにくい政策の領域」指摘の声も
地方自治に詳しい専門家は今後、廃止に踏み切る自治体は増えていくと説明します。

北九州市立大学 法学部 黒石啓太 准教授
「高度経済成長期に経済が上向いて税収も上向いている時期に多くの福祉的なサービス、制度ができてきたり拡充された経緯があります。税収にある程度余裕があって、高齢者も増えてきたという時期にこの制度が出来てきたということはあると思う。この制度がいまの人口減少の社会、少子高齢化の社会において本当に持続的な仕組みかが問われています」
しかしその一方で、敬老祝い金の廃止・存続の判断を巡っては、選挙との関わりもあり手をつけにくい面もあると指摘します。
北九州市立大学 法学部 黒石啓太 准教授
「相対的に高齢者の方が選挙にいって投票する、投票率の割合が高くて若い人は少ない。そうすると、自治体の現場で政策の意思決定を行う市町村長や議会の政治家は、選挙で再選を考えるとなると、高齢者にとって不利益になる政策はなかなか推し進めにくい。自治体の政治、政策に関わっている方の中では、手をつけにくい政策の領域」

人生100年時代といわれて久しくなりますが何のため、そして誰のための敬老祝い金なのか今、あらためてその趣旨が問われています。