四万十川で採れる「アオノリ」について知ってもらおうと、四万十市郷土博物館で企画展が開かれています。
四万十川で採れる天然の「アオノリ」は豊かな風味で親しまれ、地域を代表する特産品です。

企画展では川底の「アオノリ」をかき採る櫛状の漁具などが展示されていて、明治時代から伝統的に続く「アオノリ」漁を知ることができます。

また、よく混同されがちな「アオノリ」と「アオサノリ」について、主に自生したものを収獲し料理の風味付けとして使う「アオノリ」に対し、川で養殖され、天ぷらなどにして食べる「ヒトエグサ」という海藻を地域では「アオサノリ」と呼んで親しんできたことなど、それぞれの違いがわかりやすく説明されています。

収獲量が激減している「アオノリ」ですが、原因は水温の上昇にあるとみられています。このため、四万十市の水産会社では2024年から、水温の低い地下海水をくみ上げ、陸上の施設でアオノリを養殖する新たな取り組みを行っていて、将来、地域の特産物を安定的に供給することを目指しています。
(神奈川からの観光客)
「高知出身なのでアオサという言葉自体には馴染みがあったんですけど。アオサとアオノリの違いについて、違うんだろうなと思いつつも何がどう違うのか全然わからなかったのが、まるっきり違う物だと分かった。(陸上養殖で)アオノリが続いていくっていうのを楽しみにしています」
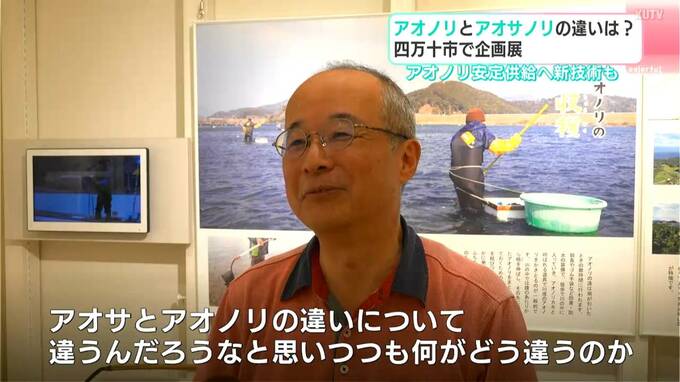
企画展は11月11日まで四万十市中村の郷土博物館で開かれています。














