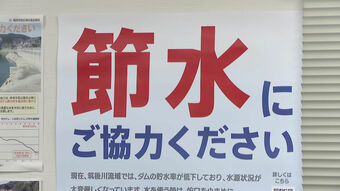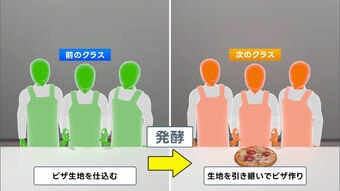「あった・なかった論争」はもう終わりに
石原慎太郎氏は「40万人の虐殺はなかった」と強い言葉で言っていましたけれども、南京事件で40万人、30万人が犠牲になったと日本の歴史学者が言っているわけではありません。人数は1万人か2万人かもしれませんが、「事件があった」という事実はあります。
中国政府が「犠牲者30万人」と言うのも、逆に日本の事件否定派が「40万人はおかしい」と言うのも、両方政治的な主張であって、事実とは分けなければいけません。本田さんのポストには、事実と政治的な主張をしっかり分けて考える姿勢が見られ、良いことだなと思います。
南京事件については、いろいろな意見がネット上で出回っています。僕は歴史学をずっと学んできて、「あったか、なかったか」という議論はもうやめてほしいと思っています。先行研究から、あったことはあった。
ただ人数はというと、当時の南京市民は30万人もいなかったという指摘があります。中国側が言う30万人の根拠はない、と僕は思っています。「その間にある事実」を見つめていくべきだろうと思っています。
誰でも「歴史」は語れる?

僕は子供の頃から歴史が好きで、歴史の本を読み続けて、大学で日本史学を専攻した歴史オタクですが、「歴史が好きだ」という人と話していると、どうもかみ合わないことがよくあります。
「歴史は勝者が書くものだから、時代が変われば変わっちゃうし」
「人それぞれの歴史があって、人の数だけ歴史観がある」
「歴史は科学じゃない」
そう言われると、「うーん、どうしたものかな……」と思います。正直に言うと、「歴史」は素人でも語れます。「徳川家康はタヌキ爺だった」とか、いくらでも遊べるんです。でも、「歴史学」は学問なので、学問としての作法を知らないと語れません。世界中どこでも、歴史学で最初に学ぶのは「史料批判」という言葉です。
(1)その史料は、出来事を実際に体験した当事者が書いたものですか?それとも伝聞ですか?2次情報ですか?
(2)そもそも、その史料は後世に書かれた偽物である可能性はないのですか?
文書の書きぶりは、公文書ならば決まっています。研究の蓄積があるので、「この時代の公文書であれば絶対にこう書きますよ」と決まっています。埴輪や土器、石器など考古学でも全部あります。石器の傷の付け方で、「これはこの時代以前にはない」とか。先行研究ではっきりしている「物差し」がたくさんあるので、後世に書かれたものであるかそうでないか、公文書ならほぼ分かります。日記はちょっと分からないですが、その時代にない言葉が入っていれば偽文書になります。
(3)その時代に書かれたものだとしても、書いたのは誰?署名があっても、別の人が書いた偽物の可能性はないか?
それから、一番大事なのは――。
(4)本人が書いたとしても、何かの意図をもって書いたものではないか?
例えば保身。「私はそんなことは言っていません!」。でも本当は言っていたりする。それから誘導。ミスリードさせるため意図を持って書かれた文章でないかどうか。こういう分析をしていくことで、この史料をどう見るかという姿勢が定まってくるのです。史料批判が一番大事。このいわば「お作法」を学ぶのが、歴史学の第一歩なのです。