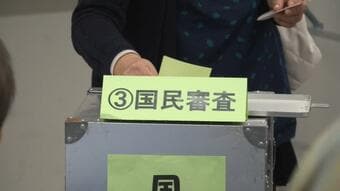沖縄の海の幸「アーサ」。和名では「ヒトエグサ」と言います。ナトリウムをはじめ、カルシウム、βカロチンが豊富に含まれていて、近年は県外への土産品としても人気があります。このアーサの大半を生産している地域があります。
櫻井記者
「ここ北中城村は県内1位のアーサ生産をほこります。そして、この干潟一面に張られた網、すべてがアーサ生産に使用されます」
今回尋ねたのは北中城村美崎の沿岸にあるアーサ養殖場。豊かな生態系が広がる干潟でのアーサ養殖は1985年ごろから始まり、現在では県内で生産されるアーサの実に7割、年間およそ20トンが北中城村で作られています。
1月ごろに収穫のピークを迎えるアーサ。干潟の一角で収穫シーズンに備え準備を進める生産者に話しを聞きました。
アーサの安里代表 安里誠さん
「自分はまだ若いんで10年ぐらいなんですけど、もう先輩たちに教えてもらいながらやってます」
『アーサの安里』代表の安里誠(あさとまこと)さん。今からおよそ10年ほど前にアーサの養殖を始めました。
安里さんは生産だけでなく、アーサの加工まで手がけ、自社で開発した『もずくとアーサぞうすい』は今年、県商工会による特産品コンテストで県知事賞を受賞しています。
Q今は何の作業をしていますか?
安里さん
「本張りの前作業というか、今から生やす段階にもっていくかたちですね」
アーサの養殖は海中に漂う天然のアーサの胞子を養殖網に付ける方法で行われます。9月初めごろに干潟に網を張り種付けをします。
安里さん
「このあたりですね、緑色をした、まだ細かい、赤ちゃんみたいな感じですね」
網に付着した、この緑色が種アーサで、およそ4か月で出荷できるほどに成長します。
種付けが終わるといったん陸に網をあげて、網に付いた泥や汚れを落とし、再び干潟に張りなおして成長するのを待ちます。
安里さん
「一日逃して何もしなかったら、本当に泥で汚れたりとかやっぱり品質が悪いアーサになってくるんで、毎日みんな朝から満ちてくるまでとか掃除とかしてますんで美味しいアーサができればいいかなと、やっぱり毎日来ることじゃないですかね、毎日の作業が一番大事です」
丹精込めて育てられたアーサはどのようにして私たちに届けられるのか、安里さんの加工場を訪ねました。加工場に入り最初に目に飛び込んできたのは大きな冷凍庫。アーサは1年を通して出荷できるよう、収穫期に1年分が冷凍保存され、カチカチに凍ったアーサは解凍され、水洗いされます。
加工場スタッフ 城間寿美子さん
「アーサについている汚れや砂を洗い落としています」
その後、網袋にいれたアーサは大胆にも家庭用洗濯機で脱水されます。入念に汚れを落とすと次はアーサについた小さなエビや砂、海藻、軽石などのゴミが取り除かれます。
加工場スタッフ 比嘉りかさん
「機械で出来ないものなので手作業でみんなで最後の作業で取り除いていってます」
この後、アーサは乾燥用と生食用に分けられ、それぞれ梱包されて出荷されます。
安里さん
「やっぱり自分も難儀して作ってますので、もう生産の段階から手間暇かけて育てているので県内の海人はがんばってますよ」
生産者により丹精込めて作られるアーサ、そんなアーサの魅力を最大限に引き出し提供しているお店があります。
店の一番人気は、やや太めの麺にゆし豆腐と北中城産のアーサをトッピングし、あつあつのそばだしをかけた「ゆしアーサそば」です。
あっさりとしたそばだしにアーサの磯の香り、これを求めて来るお客さんも多いといいます。
新里義光さん
「そば屋を始めようと思うにあたって、北中城の特産は何かなって探したところ、アーサがあるというのを見つけて、どうしても使いたいなと思って。これを求めて食べに来るお客さん、だいぶリピーターも多いんで、ずっと続けていこうと思います」
安里さん
「やっぱり美味しいものを届けたいっていう、作りたいっていうきもちですかね。北中城村の魅力も含めて、一度は現地に来て遊びに来て欲しいというかアーサをもっと食べてもらいたいですね」
北中城村美崎の沿岸を訪ねると、生産者のアーサにかける熱い想いと、たゆみなく努力する姿に出会いました。
注目の記事
「戦後最短」真冬の選挙戦 消費税減税でほとんどの各党“横並び”物価高に有効か?「食料品の消費税ゼロ」飲食店の困惑 穴埋め財源も不透明のまま…【サンデーモーニング】

“働いても働いても”…抜け出せない過酷な貧困 非正規雇用890万人 30年で広がった格差社会 政治の責任は?【報道特集】

衆議院選挙 序盤の最新情勢を徹底解説 自民「単独過半数」うかがう勢い 一方で中道は大幅減か・・・結果左右する「公明票」の行方とは【edge23】

今季も驚き“ニセコ価格”カツカレー3000円でも利益は180円、VIPに人気のケータリング1回30万円でも“安い”ワケ…北海道民には遠いリゾートの経済の仕組み

5年前は部員3人「声を出すのが恥ずかしく⋯」センバツ初出場・高知農業、21世紀枠で掴んだ“夢舞台”への切符【選抜高校野球2026】

政策アンケート全文掲載【衆議院選挙2026】