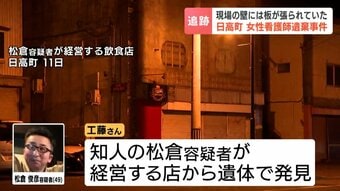2)被害の大きさ、深刻さについて
本件は、長時間にわたり複数の不適切指導が行われた事案であり、直接被害を受けた児童のほか、その言動を見聞きした児童も多数に及ぶものと推察され、男性教諭の粗暴で威圧的な言動に恐怖を覚えた児童は相当数に上る可能性があると考えております。
さらに被害児童らは低学年の児童であり、特別支援学級の児童であること、「教育」という名の下で行われていたことに照らせば、その心身に与える悪影響がさらに深刻なものになったことは明らかです。
まだ幼い児童が、上記のような粗暴な言動を受け、あるいは同級生が被害を受けていた場面を目撃していたわけですから、強い恐怖心を植えつけられていたことは当然ですし、その心の傷は、簡単に癒えるものではありません。
3)市教委の対応の問題点について
B校の被害児童保護者らは、複数回にわたり、管理職や市教委に男性教諭の指導につき相談を行っておりましたが、適切な対応はなく、積極的に事実関係を調査しようとする姿勢も皆無でした。
本件で市教委が第三者調査にようやく踏み切ったのは、一部報道でこの問題が大きく取り扱われた後でした。あまりにも、遅すぎる対応と言わざるを得ません。
本件の2件の調査において、当時の市教委の体制、管理職の対応については厳しい指摘がなされたと聞いておりますが、当然の結果であると考えます。
とりわけ、2019年3月に、女性教諭が市教委内部の相談窓口に対し、A校での男性教諭の児童に対する不適切指導が相談したにもかかわらず、特段調査等を行わなかったことについては、一連の市教委対応の中でも最大の問題と考えております。
仮にこの時点で上記女性教諭の訴えに真摯に耳を傾け、その重大さを理解し、体罰・不適切指導の事実関係調査を行い、有効かつ適切な指導を行っていれば、B校でも同様の被害が起こることは防げたのではないでしょうか。
この時点で対応をしなかった原因について、市教委担当者に質問をしましたが、残念ながら、10日時点においては納得できる回答はありませんでした。
。
本件において、市教委は、適正な情報提供を行った女性教諭を切り捨て、結果的に加害者である男性教諭を守り続けました。その安易な判断が、体罰・不適切指導を助長し続けたと言っても過言ではなく、責任は重大であると考えます。
注目の記事
“車版”モバイルバッテリーが救世主に?! バッテリー上がりにジャンプスターターが活躍 スマホ充電が可能な商品も 車のプロに“冬の運転”聞いてみた

「許せない、真実を知りたい」 中古ランドクルーザー480万円で購入も 未納車のまま販売店倒産へ 全国42人同様の被害訴え 店側の弁護士は「納車困難なのに注文受けていたわけでない」

久米宏さん「殺されてもいい覚悟」と居酒屋で学生と「ピッタシカンカン!」の素顔 落語家・林家彦いちさんに聞く『久米宏、ラジオなんですけど』TBSラジオで15年共演

南鳥島沖だけではない、日本の山に眠る「レアアース」 新鉱物が問う“資源大国”の夢と現実「技術革新がないと、資源化できる規模の採掘は見込めない」愛媛

【富山地鉄】維持か寸断か「なくなったら静かやろうね」廃線危機の電鉄魚津駅前 老舗たい焼き店主が漏らす…消えゆく街への不安【前編】

"理想の条件"で選んだ夫が消えた…27歳女性が落ちたタイパ重視の「恋の罠」 20代の5人に1人が使うマッチングアプリ【前編】