多くの県民が犠牲となった沖縄戦からその後27年続いた米国統治、そして本土復帰。激動の時代と重なるように皇室に対する県民感情も複雑に変化してきました。
6月4日から2日間の日程で沖縄を訪れた天皇皇后両陛下と愛子さま。県内は歓迎ムードに包まれましたが、5日、那覇市内では抗議する人たちの姿もありました。
かつて、天皇の名の下に戦争へと突き進んだ日本。太平洋戦争末期、沖縄は米軍の激しい攻撃にさらされました。

日本軍は国体護持、つまり天皇制を維持するため沖縄での徹底的な戦略持久戦を選択し、その結果、多くの住民が戦闘に巻き込まれ県民の4人に1人が命を落としました。
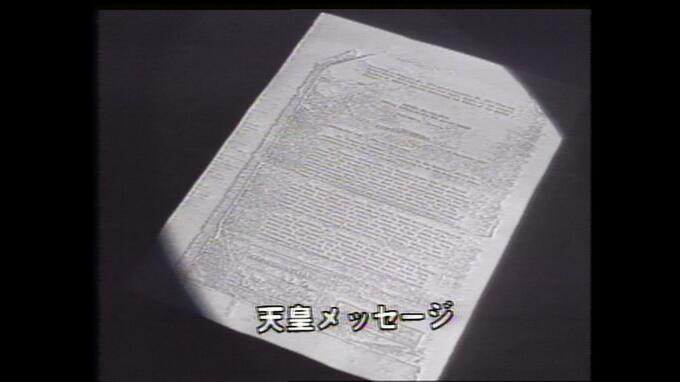
戦後、米軍の統治下に置かれることとなった沖縄。終戦から2年後の1947年(昭和22年)沖縄の軍事占領継続を望むと、天皇が米側に伝えていたことが後に明らかとなります。いわゆる「天皇メッセージ」です。
1952年(昭和27年)、サンフランシスコ講和条約によって日本は主権を回復しますが、沖縄では米軍による強権的な基地建設が本格化していくこととなります。

1987年(昭和62年)に沖縄で開催された海邦国体。国旗の掲揚、国歌斉唱は県民に様々な感情をもたらしました。
▼「日の丸」掲揚・「君が代」斉唱時に起立しなかった男性
「国体は成功させてほしいと思うんですが、やっぱり日の丸掲揚、君が代斉唱、我々に言わせればまさに押しつけなんですが、国体という場を利用して、まさに政治的利用ですよ。県民にどういう美辞麗句を並べようが、それは空手形にしかなりません」
国旗・国歌への反発は、読谷村のソフトボール会場で日の丸が焼き捨てられるという事件へとつながりました。

結局、沖縄を訪れることを強く希望していたとされる昭和天皇の願いが叶うことはありませんでした。
▼昭和天皇ご逝去の報に接した男性
「生きている間に、一度はぜひ沖縄に来てもらいたかったですね」
慰霊を重ねた上皇ご夫妻 受け継がれた思い

戦後、今の上皇さまが初めて沖縄を訪れたのは皇太子時代の1975年。ひめゆりの塔を訪れた際には過激派に火炎瓶を投げつけられるという事件も起きました。しかし、その後も上皇ご夫妻は、繰り返し沖縄を訪れ、戦争体験など県民の声に耳を傾け続けてきました。
そしてそれは、戦争を直接知らない天皇陛下へと受け継がれ、沖縄での慰霊を重ねる皇室の姿を、県民は見つめてきました。
かつて、賛否両論を巻き起こした皇室による沖縄訪問。戦後80年が経ち、県民の皇室に対する感情も大きく変化しています。















