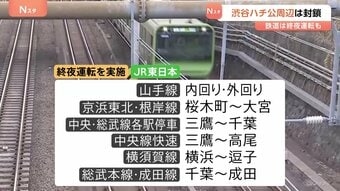小中高生のゲーム課金相談増

出水キャスター:
ゲーム機を楽しむ小中高生が増えるなか、ゲームの課金相談も増えています。国民生活センターによりますと小中高生のインターネットゲームの相談件数は2023年は4272件もあったというのです。
実際に事業者に支払った金額の平均額は▼小学生 10万5741円
▼中学生 19万3366円 ▼高校生 22万6032円と、驚きの金額になっています。
経済アナリスト 馬渕磨理子 さん:
子どもが消費する値段ではないですね。
井上貴博キャスター:
(ゲームの課金は)クレジットカードで引き落としができるので、親のカードを使ってしまったということもあると思います。
どんな対策がある?ゲーム課金

出水キャスター:
国民生活センターでは様々な対策を紹介しています。
1)『子どもと一緒にプレーに関するルールを作ること』
プレー時間、月の課金はいくらまでというルールを一緒に決め、子どもに納得してもらう
2)『ペアレンタルコントロール』の利用
ゲームに使用するタブレットやゲーム機自体に保護者が利用制限を設ける機能。気軽に他者との交流ができないように、知らない人との会話をブロックするなどといった設定もできる
3)『クレジットカードやパスワードなどの情報や設定を確認』
子どもが勝手に課金できないように、デバイスなどに記憶させているものを見直すこと
経済アナリスト 馬渕磨理子 さん:
「ルール作り」はすごく大事だと思います。規制をかけると、それをかいくぐってしまう可能性もあります。
じっくり話し合って「毎月ここまではいいよ」「こういった使い方はしないで」といったルール作りが大切ですね。
井上キャスター:
ゲームが子どもに与える影響は負の面ばかりではなく、世界が広がるというプラスの面もあります。多くの保護者はその両立が難しく悩まれているのかなと思います。
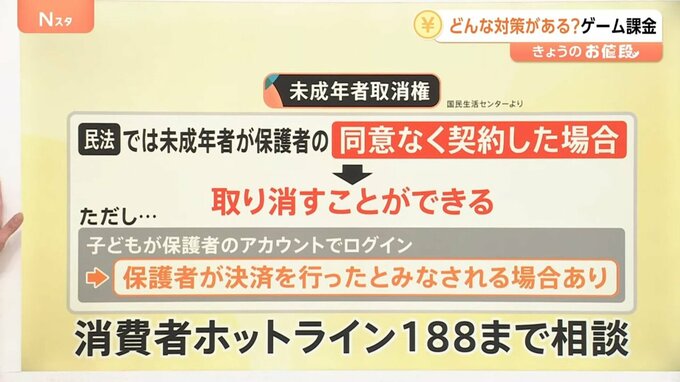
出水キャスター:
国民生活センターによりますと、実際に子どもが親の同意を得ずに課金をした場合、民法で定められた「未成年者取消権」によってその契約を取り消すことができるということです。
ただ、保護者のアカウントでログインし、保護者が決済を行ったと見なされる場合もありますので『消費者ホットライン 188』まで相談をしてください。