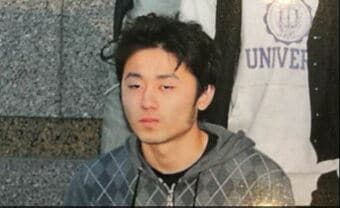上高地に通じる歴史的な登山道で起きた大規模な土砂崩落は、少なくとも高さおよそ30メートル、長さおよそ20メートルにわたることが分かりました。
また、土砂崩落が発生した場所は、2020年に起きた崩落と同じ場所であることも分かりました。
土砂崩落が起きたのは、松本市安曇の島々地区の登山口から徳本峠(とくごうとうげ)を通って上高地の明神に通じる、全長20キロの登山道「島々明神線歩道」で、島々宿登山口から徳本峠までの16キロの区間が、4月9日から通行止めとなっています。

県では、4月23日に、松本市や環境省、登山道の整備を行っているボランティア団体の「1095(トクゴー)登山整備隊」と、現地調査を行いました。

県によりますと、崩落した場所には、長さ30メートルの鎖が設置されていましたが、半分ほどが土砂で埋まっていて、崩落は少なくとも高さおよそ30メートル、長さおよそ20メートルにわたっていました。

島々明神線歩道では、2020年に大雨や群発地震による斜面の崩落が起き、2024年の9月まで同じ区間が通行止めとなっていましたが、今回の崩落も同じ場所で起きていました。
島々明神線歩道は、釜トンネルが整備される以前は、上高地に至る唯一の道で、日本アルプスを初めて世界に紹介したウォルター・ウェストンが歩いたことでも知られる歴史的な登山道です。
県では、今回の現地調査をもとに、う回路も含めて復旧の方法などを検討することにしていますが、前回の崩落でも復旧までに4年を要したことから、今回も開通までには一定程度の時間がかかりそうです。