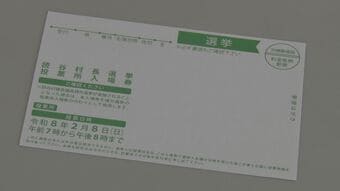沖縄本島北部・中部ではウリ科の植物に被害をもたらすセグロウリミバエが確認されていて、農林水産省は根絶に向けた「緊急防除」を14日からスタートさせました。
その一環としてゴーヤーやトマトなどセグロウリミバエが付着する恐れがある野菜や果物を本島の外へ出荷する際の移動検査が始まり、豊見城市のトマト選果場では、光センサーで大きさや密度を選別する通常の作業に加えて、セグロウリミバエがいないか職員による目視確認が行われました。
トマトをいれた箱の取っ手や空気穴はテープでふさがれ、移動中のセグロウリミバエの侵入を防ぐ措置がとられました。
――穴をふさぐことで手間はかかりますか?
▼豊見城市選果場 職員「そうです。すごくかかります。(作業が)今までなかったので、結構な量が出てきますので、すごく大変ではあります」
14日は1750ケースに合格のラベルが貼られ、約3割が本島外に出荷されたということです。
この選果場にミニトマトをだしている農家はビニールハウスにセグロウリミバエが侵入しないよう注意を払いつつ、危機感をもって現状を見ています。
▼農家 長嶺隆さん「県外に出せなくて、沖縄に(野菜が)溢れてきたら、値段的にも下がるよね。それはちょっと心配になるね。自分たちはこれで飯食ってるもんだから、どこから入ってくるかわからないものだからね」
またJAおきなわは、対象となる野菜や果物の苗木や種の一般への販売を今月から控えていて、すでに庭先などで栽培している人には、自粛や、ビニールハウス栽培にするなど管理の徹底を呼びかけています。