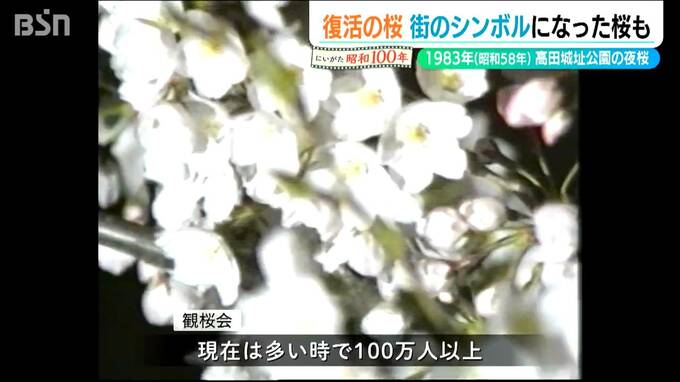今年が昭和で数えるとちょうど100年ということから、BSN新潟放送のライブラリーに眠る映像で『昭和の新潟』を振り返ります。今回は『桜』です。
1954年(昭和29年) 加治川の桜(県政ニュースより)
【当時のナレーション】
『加治川の清い流れに沿って爛漫と咲き乱れるソメイヨシノサクラは本県の誇る名所の一つです』
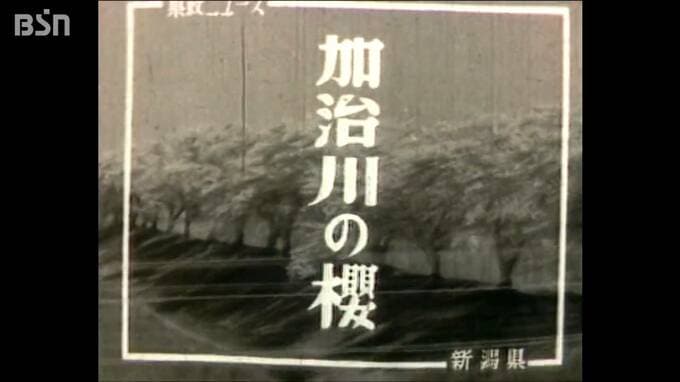
『国立公園 飯豊連峰の残雪を背に、その絵のような美しさは、時とともに堤の上を埋め尽くした花見客で賑わっております』

実はこの加治川沿いの桜は昭和41年の集中豪雨、昭和42年の羽越水害や河川改修によりその姿は一度失われたそうで、水害前の貴重な映像となっています。
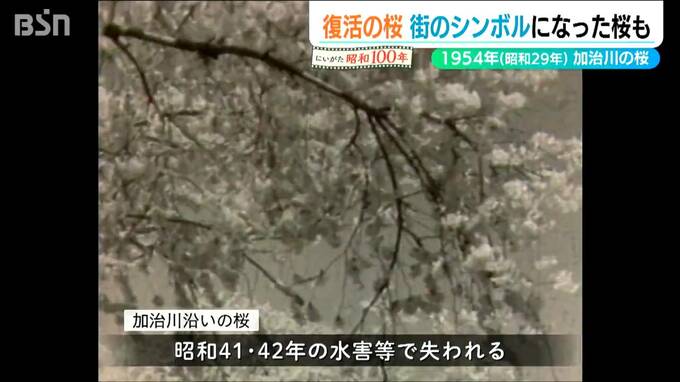
その後、復元の声が高まり今では再び美しい桜の姿を見せています。

1975年 分水おいらん道中
こちらは1975年、昭和50年の大河津分水の桜です。

桜に合わせて行われる分水おいらん道中。
3人のおいらんが“外八文字”という独特の歩き方で桜並木を練り歩く様子は、令和の現在とほとんど同じです。
【当時のナレーション】
『最近は、消えていきがちな昔ながらの風俗行事を今のうちに一目見ておこうという風潮が強まり、訪れる人々も年々数をましているそうです』

本当にきらびやかな行列ですね。
去年は1万6千人の観客が訪れた分水おいらん道中。今年は13日の日曜日に開催されます。

1980年 高田公園(現在は高田城址公園)の夜桜
続いては1980年=昭和55年のニュース映像から。
夜桜で有名な現在の上越市高田城址公園です。

【当時のナレーション】
『3千本の桜がお堀を囲み、ぼんぼりの明かりが桜の花を浮かび上がらせている上越市の城跡公園です』

『夕べは8千人の人が花見の宴を繰り広げました』

このころは10日間で30万人が訪れていたという観桜会。今では開催期間も20日前後となり、多い時で100万人以上が訪れる高田の一大イベントにもなっています。