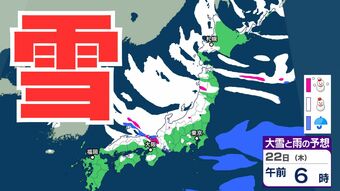動物を事故から守るため設置したのは「音」を出す装置
2020年、瀬戸内市を走っていた辻教授の車です。
ドン!
画面右下から突然現れた大きなイノシシ。

(岡山理科大学研究社会連携機構 辻維周特担教授)
「ここのシャフトが曲がってしまって」

動物にとっても不幸な事故を減らそうと設置するのは、音を出す装置。人間と動物との境界を作ろうというもので、音のパターンは動物の種類ごとにさまざまに設計しています。
(岡山理科大学研究社会連携機構 辻維周特担教授)
「これがセンサーです。このセンサーの前を(動物が)横切ると音が出る」

装置を開発した山梨県の企業T.M.WORKSと全国各地で実験を重ねてきました。シカが列車にはねられる事故が頻発していた鳥取県の若桜鉄道に設置したのは高い音を出す装置。
事故を劇的に減らしました。
こちらは北海道。メロン農家に被害をもたらしていた動物は…
クマです。
さらには、街をふんだらけにするムクドリ。
こうした活動の原点は、かつて石垣島に住んでいた教授が生き物が道路で轢かれ、死ぬことに心を痛め、毎日続けた調査や、啓発でした。
15年ほどを経て、ロードキルを防ぐ活動に研究成果が生かされることになったのです。
(岡山理科大学研究社会連携機構 辻維周特担教授)
「原点回帰したっていうことですね、地元の人、観光客から冷笑、冷たい視線を浴びたりすることも多かった。でも今やっとそういうものに耐えてここまできたかなというのは感慨深い。15年ぐらいかかりましたかね」
小さな命を守るために、音で気づかせ遠ざける。ロードキル問題解決を目指す産学連携の取り組みです。