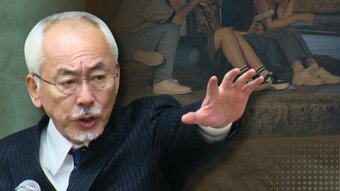「のんき」な「ユニコーン」
神戸:引き続き、外国語の語源がある言葉。「うにこうる」、これは、ちょっと元の言葉と似ているかな。でも難しいか……。一角獣のことを何と?
下田:ユニコーン。
神戸:そう!一角獣は実際にいるじゃないですか。鼻に角がある海獣「イッカク」。その牙を粉末にし、解熱剤にします。よく動物の骨は薬になりますが、その一つで、「イッカク」の角を削って粉にした薬を、「うにこうる」と言って販売していました。だけど、偽の薬がほとんどなんですよ。だから、「うにこうる」は、「嘘」という意味でも使われていた。
下田:ひゃはは!
神戸:でも、これも外国語、ユニコーンですよ。ちょんまげした人たちが「ユニコーン」と言ってるんですよ。「うにこうる、いっちょくれ!」「どうせこんなものは効かねえ、うにこうるだろう?」。
下田:嘘っていうことですね。
神戸:もう一つ外国語の言葉、「のんき」。今でも使いますね。『江戸語の辞典』では、「暖気」と漢字で書いてるんです。宋(中国の国名)の言葉で、暖を「ナン」と言っていた。「ナンキ」がなまって「のんき」になったのだ、と。「気持ちがのびのびすること」「気楽」という意味で江戸時代に使われていましたが、元々は中国の言葉だったんです。
下田:へえ、渡ってきたのね。
神戸:「奴ぁ暖気だね、大平楽だね」と使っていた。
下田:でも、「のびのびしている」、どちらかと言うと肯定的な使い方ですね。今「のんきだね」と言うと、なんか、ね……。
神戸:ちょっとよろしくないかも。
武家の作法が分かる言葉
神戸:江戸ことばは、町人の言葉ですが、町人も武士のことを表現したりする時には当然、武士を意味する言葉があるわけです。また、武士の間で使われた言葉も載っています。では、「素破抜」。
下田:すっぱぬき?報道のスクープを思い浮かべますね。
神戸:その通りです。意味は「だしぬけに刀を抜くこと。みだりに刀を抜くこと」。それから転じて、江戸時代も「人の秘密を暴露する」という意味で「すっぱぬく」と言う言葉を使っていました。これは、刀を抜くところから始まっているのですよ。「いきなり素破抜いちゃいけねえ。あぶねえだろう、先生!」とかね。誤解しちゃいけないんですが、庶民も脇差(わきざし)は差しているんです。「脇差をすっぱ抜く」という言い方もできると思いますね。
神戸:そして武士同士の習わしとして、刀の刃と刃、鍔(つば)と鍔を、カチーンと鳴らす様子が時々、時代劇でありますね。あれを「金打(きんちょう)」と言います。武士と武士が、男と男の約束を交わす時、「相違ないな?」「わしの決意は変わらぬ」「よし!」カチーン。かっこいいでしょ。
下田:ほー、いいですね。小説のワンシーンですね。
神戸:そう!ちなみに、女性と女性は手鏡です。手鏡と手鏡を合わせて鳴らす。心を違わないということですね。これもなかなかいいでしょう?
神戸:刀の話だと、もう一つあります。「切刃を廻す(きっぱをまわす)」。つまり刀の峰の反対、切れる方を「切刃」と言うのですが、刀を左の腰に差す時、いつもは刃を下に向けて帯びているんです。ところが、いざ抜くときはカチャッとひっくり返す。上に刃を向けて、右手をかけて鞘(さや)からすっぱ抜くわけですね。刃を上に向けることを、「切刃を廻す」。切刃を廻すときには警戒を意味することが多いです。トランプ大統領とゼレンスキー大統領、話をしていたら突然切刃を廻しちゃった。江戸語で言ったら、「切刃を廻しちゃいけねえ、この後戻れねぞ」みたいな。