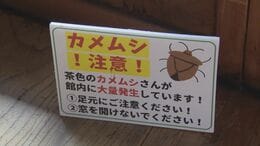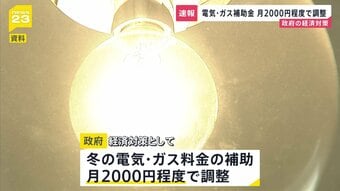「君たちは未来への宝だ ~相撲のチカラで世界にはばたけ~」をキャッチフレーズに、大相撲元横綱・白鵬の宮城野親方が創設した第15回白鵬杯世界少年相撲大会が建国記念日の11日、東京・国技館で開催された。参加したのは日本を含めて14カ国・地域からの約1100人に及ぶ幼児、小学生、中学生世代の子どもたち。館内には各国の国旗が掲揚され、指導者、父兄らの歓声とともに、拍手と笑顔があふれる1日になった。
午前9時前から始まった開会式では、現在宮城野親方が所属する伊勢ケ浜部屋の師匠である伊勢ケ浜親方(元横綱旭富士)が「この大会を目標に稽古を積んできたと思う。けがをしないように頑張ってください」と挨拶した。それに続き、マイクを握った宮城野親方は「戦禍の続くウクライナのチームが参加してくれた。皆さん、温かい拍手を」と5人の同国選手団を歓迎した。さらに「石川県では大変な地震があった。能登の皆さんも1年間、大変な思いをして稽古してきた。拍手を」と能登小木道場を含めた被災地からの参加クラブへも館内からの激励を促し、友好的な雰囲気が高まった中で試合が開始された。
個人戦は、幼児クラスのほか小学生が学年別、中学生は1~3年まとめての実施。団体戦は小、中学生混同の5人制に100チームが参加した。5回目の出場となるウクライナチームは奮闘。団体戦では8組に分かれたブロックの初戦2回戦でウズベキスタン、3回戦でタイを破り、ブロック決勝に進出した。最後は全体で準優勝したモンゴルに1-4で敗れたが、力は出し切れたように見えた。
昨年九州場所で新入幕、今年の初場所で十両優勝した獅子や、3月の春場所で新入幕濃厚の安青錦の同国出身2関取も応援に駆け付けた。団体戦で3番手の中堅を務めて2勝1敗だった小学6年のグリツコフ・イェフヘン君は、「最高の大会だった。獅子さんのような強い投げを打ちたい。将来は日本で大相撲入りして一番を目指したい」と話した。
白鵬杯は宮城野親方が現役だった2010年に大阪府堺市の大浜公園相撲場で、日本と親方の母国であるモンゴルから741人が参加して始まった。その後、12年は未開催だったが、14年の第4回大会から開催場所を国技館に移した。参加国、参加人数も徐々に増え、16年の第6回大会からは1千人を超える規模になっている(コロナ禍の21年第11回大会は中止)。
海外ではマットを敷いた土俵での練習がほとんどだという。このため、土の土俵の感触を覚えてもらおうと大会前日に海外チームの合同練習があった。白まわしを付けた宮城野親方の直接指導を見たが、とても丁寧だった。
「まずはシコの踏み方を教えます。シコは見ている人も、実際にやる人も動きが単純なので面白くない。でも、シコはすごく大切です。お相撲さんが立ち合いにぶつかった時の衝撃は1トン(t)あると言われている。それに耐えられる足と腰を鍛える。単純な動きと思わないで、練習することが大事。じゃあ、みんなでシコを踏みましょう。1、2、3。2、2、3。足を降ろした時に『ヨイショ』と言いましょう」
子どもたちの目を直接見ながら自らが手本を示し、語り掛けるように相撲の基本を伝える。通訳の声を聞き、真剣に取り組む子どもたち。すり足や力士との稽古等を含めた約2時間半を終えると、最後には親御さんらも含めて写真撮影に応じ、大会への気分を盛り上げていた。
そこに、ジョージア相撲連盟の理事長を務める元小結・黒海のレヴァン・ツァグリア氏もいた。昨年からこの大会に選手を連れてきているというツァグリア氏は、「去年、この大会に参加したみんなが、相撲を好きになった。白鵬杯のような子どもの大会は世界でもない。相撲が世界に広がる。とても良いこと。将来は、(自分や元大関栃ノ心らに続く)ジョージア出身の力士を大相撲の世界に送り込みたい」と嬉しそうに話した。
海外勢は総勢60人弱。宮城野親方は残りの1千人以上、9割を超える日本の子どもたちへの気遣いも忘れない。この日は見届けた勝負には必ず拍手を送り、選手や周りの関係者には穏やかな表情で優しく声を掛けていた。実は昨年3月、弟子の暴力問題が明るみになって宮城野部屋が閉鎖されることになり、今年の大会開催は危ぶまれていた。「子どもたちの熱い声と相撲協会の先輩方の熱い声があって、今年も開催出来ることになった。本当に良かった。主役は子どもたちですから」と胸をなでおろしていた。
中学生の相撲競技は水泳、体操、ハンドボールらとともに、少子化による部の設置率の低さや教員の負担軽減等を目的に2027年度から全国中学体育大会(全中)で廃止が決まっている。「相撲が全中から無くなる。この大会は唯一、プロの力士とも触れ合える夢舞台。一生懸命、稽古している子どもたちが活躍する場が少なくなっているだけに、何とかこれからもこの大会を続けていければ」と、言葉に力を込めた。
それは15年の第5回大会から関わっている実行委員会の永井明慶・大会運営責任者も同じだ。「以前は四国や中国地方からの参加は少なかったが、今は国内のいろんな地域からチームが出てくる。都道府県予選を勝ち抜くような強いチーム、選手だけでなく、相撲が好きな子どもたちみんなに、殿堂である国技館の土俵で相撲を取らせてやりたい。初期の頃から掲げるこの大会の趣旨、願いはずっと変わらない」と語る。
白鵬杯出場経験者で角界入りしている現役力士も増えてきた。昨年2度の優勝を飾り、大関に昇進した大の里を筆頭に、昨年春場所で110年ぶりの新入幕優勝を果たした尊富士も。力を付けてきた熱海富士、伯桜鵬。十両には白熊、木竜皇がいる。高校生になってからレスリング留学で来日した新横綱・豊昇龍は当然、出場経験はないが、土俵をはく手伝いをしたことがあるという。
最後に宮城野親方が「きょうは長い時間、ありがとうございました。団体戦、個人戦の決勝には感激した。来年、また会いましょう」と挨拶。「三本締め」で全日程を終了した時には夕方17時半近く。帰り道は夕暮れだった。
終日、館内の通路や土俵の脇で組み合ってじゃれ合う子どもたちからは笑い声が響いていた。中には負けて、悔し涙にくれる子もいたが、それも貴重な思い出として幼い心に残っていくだろう。まさに世界中の「宝」に夢とやる気を与える大会だと感じた。
(竹園隆浩/スポーツライター)