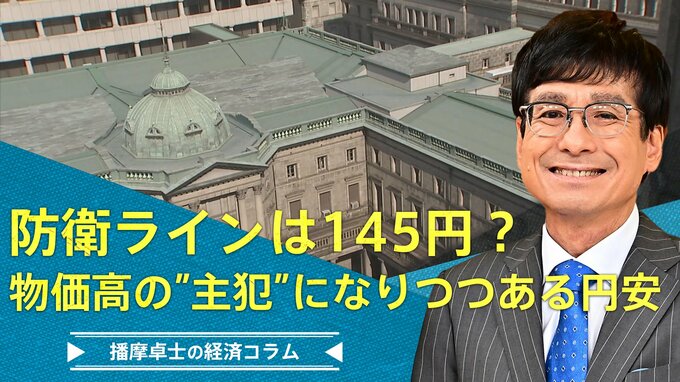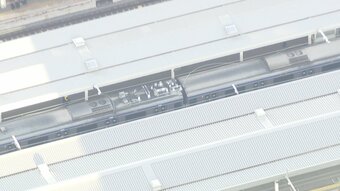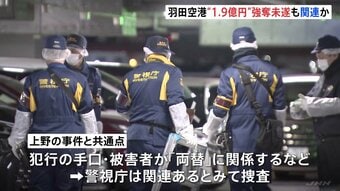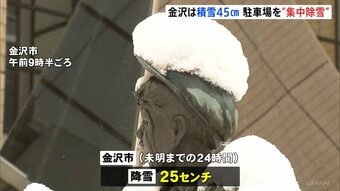日銀が9月13日に発表した8月の企業物価指数は、前年同月比で9.0%上昇となり、1980年以来の高い上昇率が続いています。中でも輸入物価は、円ベースでは前の年に比べて42.5%もの極めて大幅な上昇です。その一方、ドルなどの契約通貨ベースの輸入物価は21.7%の上昇でした。つまり輸入価格の上昇のうち、およそ半分が円安によるものということになります。
これまで物価高騰は、ウクライナ戦争などによる原油や穀物価格の上昇が主因で、円安がそれに拍車をかけるという構図でしたが、ここに来て原油価格や国際小麦価格は落ち着く一方、円安は一段と進んでおり、少なくとも卸売段階での輸入品値上がりの『主犯』は、円安になりつつあるのです。この動きは価格転嫁を通じて、これから消費者価格に押し寄せてくることになります。
■強まる円安圧力、米国発CPIショック
その円安は止まる気配がありません。
注目されたアメリカの8月の消費者物価指数は、前年同月比で8.3%の上昇でした。7月の8.5%より伸びは小さくなったものの、足元のガソリン価格の値下がりが大きかった割に、他の価格上昇が大きく、食料品とエネルギーを除くコア指数は前年比で6.3%、前月比でも0.6%と、いずれも伸びが加速しており、見れば見るほど悪い内容です。新車や衣料品の上昇が再加速した上、賃金上昇が幅広いサービス価格の上昇につながっている構図が見て取れます。
これを受けて、中央銀行のFRBが大幅利上げを続けるとの見方から、金融市場には再び「CPIショック」が走り、円は1ドル=144円台後半まで売り込まれました。焦点のアメリカの長期金利は再び3.4%台まで上がり、6月につけた3.5%を超えるかどうかが当面の焦点になるでしょう。
また、9月15日に発表された、8月の日本の貿易赤字は2兆8173億円と、単月として過去最大を記録しました。高止まりするエネルギー価格や円安がその原因ですが、貿易赤字が増大すれば、代金支払いに充てるドルを手当てする必要が増えるので、実需面からも、円安圧力は増すことになります。円安が貿易赤字を招き、それがまた円安を招く構図です。
■レートチェックで高まる介入警戒感
こうした円安圧力を受けて、「いつまでたっても注視するだけ」と揶揄された財務省が伝家の宝刀である為替市場への介入に向け、大きく踏み込ました。為替市場介入は財務省にその決定権限があり、実務を日銀が担当することになっていますが、14日には、日銀が個別の金融機関に対し為替相場の水準を尋ねる「レートチェック」を実施しました。
「レートチェック」は市場介入の準備として行われてきたのが常です。関係者によれば、14日のレートチェックは、1ドル=144円90銭近傍になったところで実施され、その『尋ね方』は前回、1998年の『円買い・ドル売り介入』の時と同じだったということで、外国為替市場には一気に緊張感が走りました。
同日夕、介入について問われた鈴木財務大臣は「やるときは間髪入れずに、瞬時に行う」と、これまでの慎重さと打って変わって踏み込んだ発言を行った他、財務省の神田財務官も「適切な対応をとる準備ができている」と述べました。いずれの発言も、市場介入について事前にアメリカから何らかの同意を取り付けたと思わせる発言です。
総理動静によれば、神田財務官は12日午後と13日午前に総理大臣官邸で岸田総理大臣に面会しています。この時期に、財務官が鈴木財務大臣ではなく、直接、岸田総理に会って報告すべきことと言えば、「介入についてアメリカとどういう話をつけたか(或いは、つけられなかったか)」しかないように思えます。
■防衛ラインは1ドル=145円か?
アメリカと何らかの合意ができたのかを、現時点で確認することはできません。しかし、145円目前のタイミングでレートチェックが行われたことを考えれば、政府(財務省)が当面、1ドル=145円を防衛ラインと考えていることが容易に想像できます。24年前の円安は、147円64銭が最安値です。このラインを突破すれば、あとは事実上の壁がなくなることから、歯止めの効かない円安に陥るリスクが出てきます。のりしろを考えれば、その手前の145円にまずは防衛ラインを引くことに違和感はありません。
しかし、財務省の決意と、それがうまくいくかどうかは別問題です。仮にアメリカの同意を取り付け、市場介入が行えたとしても、アメリカは、市場介入を「限定的な特例」としか認めないでしょうし、ドル売り介入には手持ちのドルを売らなければならないという物理的な制約があります。何度も使える手ではないのです。
何より根源的な問題は、政府が「物価高や円安を止めたい」と思っているのに対し、日銀(特に黒田総裁)は、本音では「物価高・円安は好ましい」と思っていることです。物価高や円安を止めるには、まず超金融緩和の修正が政策の「基本中のキ」なのに、それが変わらないという足並みの乱れを、市場は必ず突いてくるでしょう。物価高対策に必死の岸田総理は今のところ、黒田総裁の言うことも聞いて、折り合いをつけようとしていますが、異次元緩和の総括を先送りするだけでは、この嵐は乗り切れそうにありません。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)