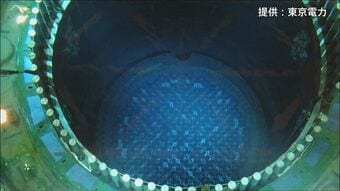「とんでもない株式が期末にはどこかへ飛んでいく」
違法な「利回り保証」に端を発し、顧客の損失を引き取る判断をして「あてのない相場回復」を待ちながら、山一証券の「簿外債務」は拡大し続けた。
しかし、その間に、何度も損失を開示しようという動きもありながら、その都度、同社の経営サイドがつぶし、問題の「先送り」が繰り返された。
1990年代の半ばにかけて、一部の役員も「簿外債務」の存在を知ることになる。
1993年8月13日、山一証券は専務ら8人の首脳が秘密会議を開き、表の帳簿には書いてない「ペーパーカンパニー」などを含めた損失について、対応を話し合った。
しかし、結論は出なかった。
報告書によると、出席者はこう証言する。
「会議で一括償却の話が出たが、どうやってやるのか、誰にも答えがなかった」
「決算も状況も微妙で、経営の判断としては『先送り』するしかないだろうという内容で、その場の雰囲気もそうだった。会議の主旨が何であったのか、疑問に思った。わが社特有の、結論の出ないファジーなままの会議だった」
1995年になると、役員の一部から「すべてを明らかにして、徹底的に議論して対策を立てるべき」という意見が持ち上がったという。
そこで常務以上の役員を対象にした、泊まり込みの会議が千葉県船橋市の研修センターで計画されていたという。しかし、当時社長だった三木のひと言で、会議は実現しなかった。
「現状の経営体力では厳しい。まだやめておいう」(三木)
山一は、経営破たんを食い止める可能性があった最後の機会を逃し、「飛ばし」によって生じた「簿外債務」を隠し続けることになる。損失が表面化することを避けていたのである。
当時、「飛ばし」の受け皿となっていた会社の元経理部長は、TBSのインタビューにこう証言した。
「期中でみれば、とんでもない株式が期末にはどこかへ飛んでいく。外に出す書類には一切、出てこない。評価損のある株式の受け皿をみつけるのは、証券会社の営業マンで、社長も知っている話だから、安心して受けてくれと言われた」
損失は、バブル経済崩壊により株価の低迷が続いた結果、最終的には山一が買い取らざるを得なくなった。そこで、今度はその損失を「ペーパーカンパニー」や「海外子会社」に移し替え、「粉飾決算」をしていたというのが、実態だった。
「飛ばしをやっていくうちに、株がどう処理されたか、わからなくなっていった。何度かやっていくうちに、心配はないという感触を得てしまい、頭も使わない、実におかしいやり方だった。また次の「飛ばし先」がなく、猛烈な損失が出ている株式を抱え込むようになった」(受け皿会社元経理部長)
こうした危機的な状況を多くの山一首脳が知ってはいたが、損失の処理を決断できずに「見て見ぬふり」をしていたのだ。最高実力者だった“山一のドン”行平や、“山一のプリンス”三木はどう考えていたのだろうか。

もし山一証券が、破たんを食い止める機会があったとすれば、それはいつだったのか、国広はこう指摘する。
「そもそも損失が生じるような営業をしなければよかったと言えますが、すでに、損失が生じていたことが前提にすれば、やはり最終的には、1995年に実施するはずだった『千葉県船橋市の研修センターでの役員合宿』がラストチャンスだったと思います。ここで、全部をさらけ出していれば、違った展開になった可能性はあるのでは」
「もちろん、大きな犠牲は伴い、非常に痛い目に遭う。例えば大赤字の決算で、リストラも避けられない。経営陣が総退陣など、いろいろあったかもしれないが、公表するという判断はあったのではないでしょうか。そこ(1995年)を超えたら難しいと思います」
「相変わらず経営陣は『神風が吹いて、株式市場が回復する』と期待していた。しかし、株価は下がる一方。そうすると結果論ですが、救う手立てがあったかどうか、そこで助かったかどうかわかりません。もちろん、それより前に隠ぺいを決めた1991年の『ホテルニューオータ二』と『ホテルパシフィック東京』の2回の秘密会議の時点で、膿を出す決断をしていたら、助かる可能性はあったと思います」(国広)
やがて「飛ばし」が山一の経営にどんな影響を及ぼすのか、具体的に話し合われた形跡はなかった。拡大する『簿外債務』の問題は常に『先送り』された。
しかし、「飛ばし」は損失を見えないようにしているだけで、結局損失が消えてしまうはずはなく、ブーメランのように戻ってくることは明らかだった。
歴史に「もし」はないが、1990年代の半ばまでに、損失を公表して処理を実施していたなら、大きな代償を払ったかもしれないが、違った展開になった可能性はあったのではないだろうか。