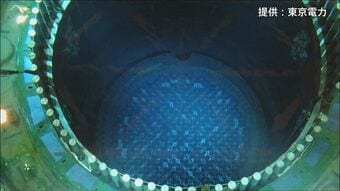「日本の金融業界では仕事こなくなるよ」
とうとう山一証券は、会社を存続させるためには大蔵省と日銀にすがる以外、方法がなくなった。
その日11月14日の夕方、野澤は大蔵省の長野証券局長を訪問、「簿外債務」の存在を初めて伝え、生き残りへの支援を求めた。
すると、長野局長は野澤社長にこう告げた。
「もっと早く来ると思ってました。(倒産した)三洋証券とは違うのでバックアップしましょう」
野澤はこれを「大蔵省は、再建を支援するという前向きな姿勢を示してくれた」と受け止めた。帰りの車の中で、同行した藤橋常務からも「よかったですね」と声を掛けられた。
実際、11月15日、16日にも藤橋常務や経理部長が大蔵省に赴き、会社再建策や含み損の状況を説明している。17日には野澤社長、藤橋常務が証券取引等監視委員会(SESC)にも含み損の報告をしている。
ところが、11月19日、野澤が大蔵省を訪問すると、長野局長の態度は一変していた。そして、こう通告した。
「感情を交えずにタンタンと言います。『自主廃業』を選択してもらいたい。金融機関としてこんな信用のない会社に免許を与えることはできない」
長野が伝えた「自主廃業」というのは、会社が自分から事業活動を止めろということだった。会社は消滅、従業員は全員解雇しなければならない。
一方で、「会社更生法」という手段であれば会社は存在できる上、従業員も残して、法的に再建をめざすことが可能だった。これより前、11月3日に経営破たんした「三洋証券」でも適用されていたからだ。
しかし、山一証券の場合は、『飛ばし』による粉飾決算という犯罪が絡んでいたため、法的整理の「会社更生法」は認められなかったのだ。
たった5日前まで、「支援する」との姿勢にとれた長野局長の態度は一変していた。
いきなり山一に「自主廃業」を迫ったのである。野澤はあまりの手のひら返しに、言葉が出なかった。
だが長野は淡々と続けた。
「大蔵省は11月26日に山一の簿外債務について発表します。同時に会社も発表してください」
野澤は、頭を下げて泣きついた。
「局長、何とか助けてください」
わずか5日間に何かがあったのだろうか。
1997年11月は日本にとって金融危機のクライマックスだった。「三洋証券」「北海道拓殖銀行」「山一証券」「徳陽シティ銀行」・・・毎週のように次々に銀行や証券会社が破綻していた。なかでも「北海道拓殖銀行」は戦後初の都市銀行の破たんとなり、金融市場をパニックに陥れた。マーケットには激震が走った。
その「たくぎん」の破たんが発表された11月17日、長野は大蔵省で緊急の対策会議を開いた。関係者によると長野は会議に先立って、山一の資産状況を精査していた日本銀行にも相談。しかし「違法行為があるところを救済などできるはずがない」と相手にされなかったという。
そこで長野は、日銀の救済が無理なら「会社更生法」は使えないか、部下と検討したが「規模が大きすぎる。違法行為もあるし、東京地裁は認めないだろう」と結論づけた。そもそも「飛ばし」を隠ぺいしていた以上、会社の存続を許すわけにもいかなかった。選択肢を一つ一つ精査していくうちに「自主廃業」しかなかったのだ。

1997年11月19日、山一証券株は、終値で「65円」まで下落。終値が100円を切るのは上場以来のことだった。
11月20日、山一証券という会社存続の唯一の方法だった「会社更生法」についても、案の定、東京地裁から門前払いだった。
「『飛ばし』という違法行為があるため「会社更生法」は使えない」との見解だった。
野澤は再び、大蔵省に赴いて長野局長と面会した。
「なんと支援をお願いできませんか、26日の発表は延期していただくわけにはいかないでしょうか」
すると長野はこう迫ったという。
「自分が野澤社長と会ったことが代議士周辺から漏れている。(なので26日ではなく)24日にも発表するので準備してくれ。これは内閣の判断です」
この「内閣の判断です」という「長野発言」の根拠がのちに問題となる。
当時のTBSニュースはこう伝えている。
『村岡官房長官は「内閣として自主廃業の方針を決めたことはない」と述べ、長野局長の発言内容を強く否定した。
この点について長野局長は、「総理や大蔵大臣に報告したものだ」と曖昧な説明をしており、村岡官房長官との食い違いを見せている』
村岡は記者会見で「内閣の関与」を「否定」したのだ。ただし、これはあとの話であって、「最後通告」を突きつけられたときの野澤は、長野の言葉を額面通り受け止めるしかなかった。情報が漏れていることを理由に大蔵省が発表を「2日も前倒し」したことに、驚きを隠せなかった。
支援どころか、大蔵省は3連休の最終日、11月24日に「自主廃業」を公表すると言っているのだ。
11月21日は連休前の金曜日だった。アメリカの格付け会社「ムーディーズ」が山一の社債の格付けを「最低ランク」の「ダブルB」に引き下げた。「投資には不適格」という烙印を押され、連休明けからの資金繰りは一段と厳しくなった。
野澤らは「これで万策つきた」と認識せざる得なかった。
連休初日、11月22日の土曜日、日本経済新聞は朝刊1面トップで「山一証券 自主廃業へ」と世紀のスクープを放った。(21日夜に日経テレコムオンラインでも速報)
このスクープが「新聞協会賞」を受賞したことは言うまでもない。
ほとんどの役員、社員は、この日経新聞の記事で初めて「自主廃業」を知らされた。野澤はぎりぎりまで逡巡し、役員会にも報告していなかったからだ。
「勤労感謝の日」の振替休日、11月24日の月曜日、山一証券は午前6時から、「臨時取締役会」を開き、「自主廃業」に向けた営業停止を決議した。
そして、午前11時半から東京証券取引所の会議室で、あの記者会見が始まった。
野澤正平社長は「私ら(経営者)が悪いんです。社員は悪くございません」と号泣した。
この会見は、平成の金融危機を象徴するシーンとして、国民の記憶に刻まれることになった。
野澤にとっては、大蔵省の長野局長に助けを求めた際、いったんは「支援する」と明言していたのに、一転して「自主廃業せよ」と突き放されたような気分だった。
もちろん「自主廃業」とは名ばかりで、山一側の自主的な判断が入る余地はなかった。
国広は、報告書に盛り込んだ野澤社長と大蔵省とのやりとりの信憑性には自信があった。
「野澤さんのような社長が大蔵省に出向くときは、必ず秘書がついていくが、野澤さんの場合は、藤橋常務が同行していました。藤橋常務は野澤さんと長野局長のやりとりを、全部ノートに記録していたのです。しかもその場で正確に。いわゆる『藤橋ノート』は、何月何日、何時にどこで誰といつ会ったのか、具体的に記されていました。その記録は極めて信憑性が高かったと思います」(国広)
周りは国広を心配したが、ぶれなかった。
「大蔵省のことを書いたら『日本の金融業界では仕事がこなくなるよ』と言われました。でも、もともと金融機関の仕事などないから関係ない、と思っていました。
大蔵省だけでなく、ここまで書くような弁護士は金融業界にとってもウェルカムじゃないよと。
報告書を書いたのは私であることはみんなわかってますから、ずいぶん心配されました。そうは言っても、大蔵省が山一の「含み損」に目をつぶっていた、黙認していたというのは、社員や国民に知らせるべき極めて重要な事実。国家的な犯罪に近いようなことだから、書かないわけにはいかないと思いました」(国広)
しかし、時代は金融ビッグバン、国広には想定外の展開となった。
「自分としては、大企業の事件は山一限りでおしまい、またマチベンに戻るものと思っていました。しかし、世の中が大きく変化したわけです。山一証券のあとも大企業がバタバタ潰れて、むしろその事実調査や原因究明の仕事の依頼がくるようになりました。高度経済成長のままだったら、私は外されたかも知れないが、金融ビッグバンにより大企業が倒れて、まったく違う世界に時代が変化した。想定外でしたが、私に「不祥事調査」というニーズが生じたんです」
「報告書を書いたときは、今後も金融機関の仕事をしようなんて、これっぽっちも考えていませんでした。山一の調査報告書は金融の仕事というより、職を失った社員たちの無念の思いに動かされて書いたもので、一つの企業がいかに失敗、転落していったかという『ルポルタージュ』だったと思います」(国広)
山一証券の粉飾決算事件と並行して、東京地検特捜部は野村証券や第一勧銀をめぐる「総会屋事件」から発展した「大蔵省接待汚職事件」の捜査を進めていた。
“聖域”と言われていた大蔵省に家宅捜索が入り、証券局課長補佐のキャリア官僚1人と、銀行局金融検査官のノンキャリら3人が収賄の罪で起訴された。
本来、公平に行われるべき大蔵省の金融検査がゆがめられていたことが浮上、大蔵省の「護送船団体制」は揺らぎはじめていた。
山一の「調査報告書」公表から10日後の1998年4月27日、大蔵省は大手証券4社や第一勧銀など金融機関から、飲食やゴルフなどの「接待」を受けていた大蔵省職員112人の大量処分を発表した。山一の破たん処理などに関わり、同期(1966年入省)のエースと言われた長野元証券局長は減給処分を受けて、大蔵省を退職した。
(つづく)
TBSテレビ情報制作局兼報道局
「THE TIME,」プロデューサー
岩花 光
■参考文献
山一証券「社内調査報告書」社内調査委員会、1998年
国広正「修羅場の経営責任」文藝春秋、2011年
清武英利「しんがり 山一証券最後の12人」講談社、2015年
西野智彦「日銀漂流」岩波書店、2020年
読売新聞社会部「会長はなぜ自殺したか」新潮社、2000年