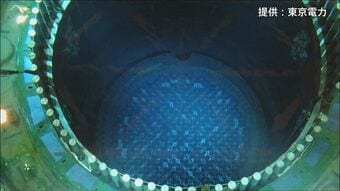「まずい事実が判明した場合でも、公表しないとは言わないでください」
それは3連休の初日だった。国広は1997年11月22日の朝、目が覚めると同時に、山一証券の「経営破たん」を知ることになる。
「土曜の朝、山一証券自主廃業という日経新聞の見出しが目に飛び込んできた。その瞬間、『自主廃業』って何だろうって。山一が自主的に廃業するとはどういうことなのかと」
週明けには、テレビで一斉に野澤社長の記者会見が中継された。このとき初めて、野澤の口から『簿外債務』や『自主廃業』という聞き慣れない言葉が飛び出す。
これは再建をめざす法的な整理手続きではなく自主廃業、つまり会社がなくなることを意味した。
「残念だけど、せっかく民暴事件やっていたのに、ああ、これで私の山一の仕事もなくなったなと思いました」(国広)
しかし、運命の糸に導かれるように、国広は山一証券の仕事に戻ることになる。
経営破たんを受けて、原因を究明するための「社内調査委員会」が設置され、委員長となった嘉本から「一緒にやってくれませんか」と打診があったのだ。
「予想もしていませんでした。嘉本さんが『調査チームには法律家が必要なんじゃないか』と言い出して、弁護士を探していた。ただし、顧問弁護士は会社に近すぎて、会社を追及することはできない。
あくまで、しがらみのない『第三者』の立場でやってくれる弁護士が誰かいないのかと。そんなとき委員長が、『そういえば、総会屋対応をしていた声の大きい弁護士がいたよな』と私のことが頭に浮かんだようです」(国広)
これに対して国広は当初、「わたしはただのミンボー専門の弁護士で、総会屋や暴力団のことはわかりますが、簿外債務のことはわからないし、証券金融の法律は詳しくないので、そんなのできないですよ」と断わろうと思ったという。
それでも、考えた末に引き受けることを決意した。「火中の栗を拾う」それは国広の信条でもあった。
「職を失う社員や国民が、一番知りたかったのは『山一はなぜ潰れることになったのか』という根本的な疑問です。
細かい証券金融の仕組みじゃなくて『なぜ簿外債務が発生したのか、それをどう隠してきたのか』という事実だろうと。
調査で事実を積み重ね、材料を集め、それに法的判断を加えながら「調査報告書」を組み立てていくのは、やはり弁護士の仕事だろうと。走りながらやれば、できるのではないかと思って、引き受けました」

調査委員会のメンバーとなった国広は社長の野澤に挨拶した。
「わたしも引き受けるからには徹底してやらせていただきますよ」
野澤は「はい」と答えたが、国広はさらに念を押した。
「まずい事実があとから判明した場合でも、公表しないとは言わないでください」
野澤は「もちろんです。しっかりやってください」と答えた。
国広は野澤に会ったとき、こう感じたという。
「『簿外債務』があったことは、山一のほとんどの社員は知らなかった。野澤さんも、破綻の3か月前に就任したので、そのときまで簿外債務の存在は知らされていなかった。だから、自分は被害者だと思っている。
『最後に社長を押し付けられた』という被害者意識。労組や社員からの吊し上げもあって『徹底した調査』を約束してくれたんです。徹底的に書いてください、という感じでした。
ところが、いざ『社内調査報告書』を公表すると、態度が急変しました。野澤さんは、ここまで詳しい調査結果が出るとは想像していなかった。山一のOBたちからも風当たりが強かった。私はそういうことも想定して、最初に約束してもらったんです」
なぜ野澤が社長になったのか。
実際、「総会屋事件」の責任をとって8月に辞任した三木淳夫社長の後任選びは難航した。それまで山一証券のトップは、行平や三木のように国立大卒でMOF担(大蔵省担当)経験のあるエリートで、法人部門や企画部門の出身者であることが慣例となっていた。
しかし、不祥事を受けた有事において社長の第一条件はまず、「総会屋事件」や「簿外債務」に関わっていないことだった。
加えて、社内政治にも縁遠い、正直で「言うことを聞く」ことが重視され、国内営業畑一筋の野澤が指名されたという。最高実力者だった「山一のドン」行平前会長や三木前社長ら、辞任した11人の役員は、そのまま『顧問』として社内に居座っていたからだ。しかし、行平と三木はのちに東京地検特捜部に逮捕、起訴される。
最後の社長となった野澤は法政大学卒、国内営業一筋から這い上がってきた。長野県の農家の四男、畑仕事が好きで実直で素朴な人柄だった。
「社員は悪くありませんから!」と号泣し、社員をかばう野澤の会見は、日本の金融危機を象徴するシーンとして海外メディアでも大きく報道された。
実はこのとき、野澤が泣きながら、社員の再就職の支援を訴えた発言。実は山一の労働組合執行部が野澤に「公の場」で発言するよう求めていた「約束」であったことが、後に明らかになった。だが、そもそも優秀な人材が多かった山一は、9割以上の社員が再就職を果たしたと報じられた。
国広ら調査チームは、12月末から約4か月間にわたって三木前社長をはじめ100人を超える関係者のヒアリングを行い、彼らの声に丁寧に耳を傾け、帳簿など大量の証拠書類の分析をした。その結果を106ページに上るドキュメントとして記録したのである。
渾身の「社内調査報告書」は、当初予定だった「全員解雇の日」の3月31日から2週間遅れたが、なんとか1998年4月16日に公表にこぎつけた。
国広は嘉本委員長らとともに記者会見に臨んだ。
「褒められるのか、けなされるのか、世の中的に評価されるかどうかは、全然わからなかった。ただ我々は全力を尽くして、やれるだけのことはやったよなという気持ちで臨んだ。
これで叩かれたら、我々の力がなかったんだからしょうがないという、覚悟というか、腹は座っていたんです。
嘉本委員長がまん中、隣の黄色いネクタイの男性(写真参照)がわたしです。おもに2人で答えていたと思います。
余談ですが、記者会見が始まる前の昼ニュースで、NHKが報告書をすっぱ抜いた。もともとNHKは、当日夜の『クロ現』で特集する予定になってたんです。でも事前に報告書の内容を見た上層部が『これはすごい』と驚いて、『どうしても会見前に報道したい』と頼み込んできた。そんなことしたら、他のメディアも怒るだろうし、何度も断ったんですが、最終的には委員長が決断して前日の夜にOKしたんです」(国広)
会見で配布された「調査報告書」には、隠ぺいに関わった経営陣や幹部が実名で記されていた。メディアの予想を裏切る生々しい内容だった。テレビは夕方のトップニュースで伝え、翌日の朝刊各紙も一面トップで大きく報じた。とくに日経金融新聞は報告書の「全文」を掲載した。そして、日経新聞本紙は記事のなかで、『歴史に残る報告書』と最大限の評価をしたのであった。