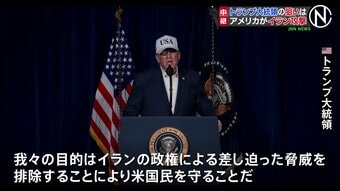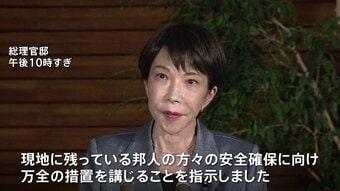主要な4人に入ってないのにネットで高く評価された安野候補
さて石丸氏については新聞やテレビなどの主要メディアが選んだ主要な4人の候補者の中には入っていた。このため、テレビ報道を見ていて彼について顔もまったく知らないという人はいないだろう。
ところが主要な4人の候補にも入っていなかったため、ほとんど無名でテレビでも扱われなかったのにネットなどで高く評価された候補がいた。
5位の15万票あまりを得た安野貴博氏だ。AIエンジニアでSF作家。東京大学工学部を卒業後にAI関連のスタートアップを複数創業した人物だという。
この人も石丸氏同様に知事選の後になってテレビなどの出演が急増している。AI技術を活用した参加型民主主義の実現を訴えて選挙戦を闘い、安野氏のマニフェストを学習した「AIあんの」が24時間有権者からの質問に答えるようにするなどテクノロジーを駆使した新しい選挙活動が一部で注目を集めていた。
選挙後に新聞社やテレビ局などに「なぜ選挙期間中に安野氏の主張を詳しく報道しなかったのか」という苦情が寄せられたという。
7月9日(火)のTBS「news23」では安野氏が生出演して、AIを活用した新しいかたちの選挙に注目して報道した。都知事選で「テクノロジーで誰も取り残さない東京をつくる」を掲げた安野氏は「(選挙戦で)テレビには0秒しか出られていない」とテレビや新聞の「時代遅れ」を指摘している。13分あまり。7月13日(土)の「情報7daysニュースキャスター」でも8分半ほど。
「TVメタデータ」を元に都知事選での安野氏の奮闘ぶりを強調して詳しく報道したと筆者が判断できる番組を筆者が独自に集計したところ、1時間4分20秒になった。
開票翌日以降での放送ではとても注目される扱いだ。しかし、これも【図3】の田母神俊雄氏の開票翌日以降の総計4時間50分に比べると、まだとても多いとはいえない数字でもある。
そういう意味では今のテレビ報道は事前に主要な候補を絞り込んでしまう弊害が際立っていることがはっきりした2024都知事選だった。テレビや新聞が絞った4人の主要候補。どこで、どのように「線引き」をしたのか。なぜ安野氏は入らなかったのだろうか。
7月24日(水)のテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」にも安野氏本人が生出演して金も組織もない中でポスター貼りなどの作業にデジタル技術を使ってボランティアを動員してゲーム感覚で実現させた舞台裏を明かした。
こちらは筆者の測定では16分近くあった。こういう選挙活動を実現する人が候補者としてどんどん登場すると、選挙そのものが面白くなるし報道そのものが活性化していくことになる。
今後のテレビの課題としては、告示前や選挙期間中などに今回の石丸氏や安野氏のような旋風をテレビが報道機関として把握・予知して、それを選挙報道にどのように加味していけるのかになってくる。
もしもネットの動きとして注目すべき候補として浮上した時にそれをどのように選挙期間中などの報道に反映させていくのか。反映させるならばどのようにするのか。主要な候補の中に入れていいのか。これまでのように主要政党の支持や支持母体などの票読みを中心にして各陣営の票を積み上げるような旧来型の選挙報道では早晩そのうち大きく読み間違える事態が起こりうる。
そういう意味ではテレビ各社が今回の「想定外」をどこまで反省して今後の教訓にしているのかは大きな課題だ。次はSNSの影響などを読み間違えずにより新しい有力候補を事前に提示していけるのだろうか。それとも従来通りの選挙報道を踏襲するだけなのだろうか。そうした岐路に立たされている現状を浮き彫りにした、今後への宿題ばかりが多い2024都知事選だった。
<執筆者略歴>
水島 宏明(みずしま・ひろあき)
1957年生。東京大学法学部卒。
札幌テレビ、日本テレビで報道記者、ロンドン・ベルリン特派員やドキュメンタリーの制作に携わる。生活保護や派遣労働、准看護師、化学物質過敏症、原子力発電の問題などで番組制作をしてきた。
「ネットカフェ難民」という造語が「新語・流行語大賞」のトップ10に。またドキュメンタリー「ネットカフェ難民」で芸術選奨・文部科学大臣賞を受ける。
2012年より法政大学社会学部教授、2016年より現職
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版(TBSメディア総研が発行)で、テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。2024年6月、原則土曜日公開・配信のウィークリーマガジンにリニューアル。