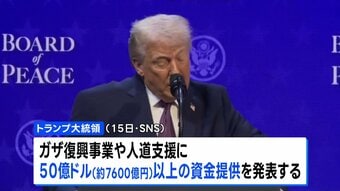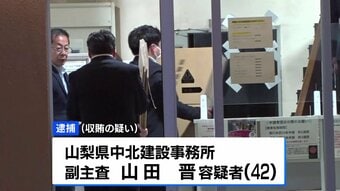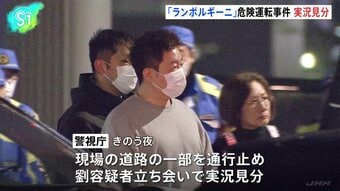コロナにより外出する機会が減り、ママ友にも会いづらい…。孤独を感じながら子育てをしている方は多いのではないでしょうか。そんな中、そもそも二人以上の乳児を連れて外出をするのが困難な多胎育児をする親は、さらに孤立を深めています。何気ない一言にモヤっとすることもあるようです。
(取材・執筆:TBS報道局 岡村仁美)
■コロナ禍でさらに孤立 同じ境遇の双子の親に出会えて涙も
2歳の双子を育てながらこの春復職した筆者。イヤイヤ期真っ盛りの娘たちを保育園の送迎のために自転車に乗せるだけでも一苦労です。自分が前の席に乗りたいと泣きわめく双子を何とか送り届けてから仕事に向かっています。
授乳・寝かしつけ・お風呂とどれを取っても一筋縄ではいかない、双子や三つ子を育てる「多胎育児」。育児の過酷さから多胎児の虐待死のリスクは一人に比べて2.5~4.0倍になるという指摘もあります(日本多胎支援協会・2017年調査)。
コロナ禍でさらに追い詰められる多胎家庭に何が求められるのか。「関東多胎ネット」の水野かおり代表と考えました。

***
岡村:
ーー水野さんも4歳の男の子の双子のママです。多胎育児に必要なサポートとはどんなものでしょうか。
「関東多胎ネット」水野かおり代表:
「関東多胎ネット」では多胎育児の経験者約50人がサポーターとして登録しています。去年からサポーターがオンラインや家庭訪問で、多胎妊婦や未就学児までの多胎児を育てる親の相談に乗る事業を行っています。オンラインの方が気軽で需要が多いのかと思ったのですが、実際に始めてみると家庭訪問をお願いしたいという人がすごく多いのです。
ーー誰かに会いたいというのはよくわかります。私は子どもが2歳になるまでイギリスで生活をしていました。0歳児二人と過ごすロックダウン中は、誰かと会って話をしないと自分がおかしくなってしまうのではと何度も思いました。双子育児について直接会って相談出来る人はいませんでした。

水野代表:
誰かに直接悩みを聞いて欲しいと思っても、悩みを共有できる人に出会えなくなっているんです。サポーターは解決策を出すというよりは、まずは利用者のお話を聞いて悩みを受け止めて、その上で自分の経験で何かお伝えできるものがあれば伝えるようにしています。基本的には傾聴して寄り添うことを大事にしています。
ーー私の場合、一番困ったのはお風呂で、双子育児を経験したことがある人に相談できたらと思っていました。まだ立つこともできない二人を同時に入れるのは難しい。洗い場のない海外の風呂場では、近くに座らせておく場所もない。双子のお風呂の入れ方について相談する人が見つからなかったので、夫がいないときはお風呂に入れるのは諦めることにしました。
水野代表:
お風呂は相談にあがることが多いです。家庭訪問が良いのは、実際に間取りを見ながらお風呂の入れ方も考えやすいところです。例えばまだ双子が歩く前だったら、脱衣場が広ければ風呂場のドアの外に一人は寝かせておいて順番に入れましょう。歩けるようになったら、二人とも同時に入れてバスタブの縁につかまってもらって同時に洗いましょうとか。住環境や子供の年齢に合わせて利用者と一緒に考えるようにしています。
また、コロナ禍で妊娠中や出産後に両親学級がなく、お父さんがお世話を学ぶ機会がないそうなんです。お母さんは病院で看護師さんなどに教わりますが、お父さんは新生児に面会もできないため、どうやってお世話をするか見ることさえできず、何もわからないまま退院してきてしまいます。
ーー退院した直後がとにかく大変でした。私の子供たちは2000gほどと小さく生まれてきました。低体重の赤ちゃんは哺乳力が弱く、退院してしばらくは母乳をうまく飲ませることができませんでした。母乳だけでは足りないので、1回の授乳で母乳→ミルクをそれぞれに。これを夜中も含めて3時間おきに繰り返すので一日中授乳をするだけで終わっていきました。
水野代表:
小さく生まれてくると普通の体重で生まれた子とお世話の違いがあるってことを、私は産んだときは全然知らなかったんですよね。全然ミルクを飲まないし、よく吐くし。哺乳力が弱かったりとか、体温調節が難しかったりとか、やっぱり泣きやすかったりとか。そういうことを事前に知っておいてもらったら、ある程度心強いかなと思って多胎妊娠中の両親学級というものもやっているんです。