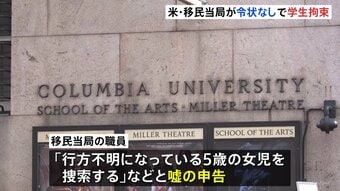■埋没林は"自然のタイムカプセル"
埋没林は今から70年ほど前に海岸で発掘されたものですが、埋没林そのものはおよそ2000年も前に、まさにこの場所にそのまま自然に生えていた杉の木と考えられています。根っこの大きさから、もとがどれほどの巨木だったかが想像できるでしょう。
今よりもずいぶん涼しい気候の時代は海面が低く、露出していた海岸近くに森林が形成されていました。気候の温暖化とともに海面の水位が上がり、水で覆われるようになった森林に砂が堆積し、木々が埋まっていったという過程があります。
ここでとても重要な役目を担っているのは、海底から湧く地下水です。この地下水のおかげで、海水の中とは違って、木は腐らずに守られているのです。ちなみに、地下水は水温15度以下のため、水槽周辺の冷涼感を演出していた正体でもあります。
埋没林は、自然のタイムカプセルでもあるということなので驚きです。埋没林の発掘時に一緒に見つかる昆虫や花粉、植物の種などは、埋没当時の環境を推定する研究に役立っています。縄文土器が発見されたこともあったそう。数千年前のことが現代からゆっくり解き明かされていくなんて、とても興味深いです。
■日本海から考える人間と自然の共存
時間軸と視点を一気に変えてみましょう。
今から2000「万」年以上も前。日本列島はユーラシア大陸と繋がっていたと考えられています。ある時、亀裂が入り、非常に長い年月をかけて日本海が誕生しました。さらに日本列島は隆起して山ができ、降り注いだ雨水は川を流れ海にそそぐ。日本海と山があるからこそ冬には日本海側に雪が降り、春には雪解け水が田畑を潤します。日本海を起源とした水の循環や恩恵が確立されていきました。日本海と人間が共存にいたるまでの地球規模のとても壮大な長編ストーリーですね。
さきほども述べましたが、埋没林が腐らずに現代にもその姿を残してくれているのは、地下水のおかげです。地下水は、山に降った雨や雪が地中に沁み込むことで湧き出ています。日本海が誕生し、山ができ、そこへ降った雨や雪が土に沁み込んでから時間をかけて湧き出た地下水が埋没林を保持し、タイムカプセルを現代に残してくれているわけです。日本海は、大雨災害の原因にもなってしまうことがある存在の一方で、人間と自然がどう共存していけばいいかを考えるきっかけを与えてくれる存在でもあると思いました。
■興味が連鎖して新しい発見・視点に
実は私にとって、海は全く身近なものではなく、むしろ少し恐怖すら感じる存在です。太陽の光が届かない海底では一体何が起きているのかと想像するだけで足がすくむような感覚になります。でも、怖いもの見たさに少し似ているのかもしれません。よく知らないからこそ非常に気になる存在です。今回は日本海について書きましたが、オホーツク海のことも非常に気になっています。
自分の気になるものが発端で、その対象周辺の他のものへと繋がり、別のストーリーが見えてくる。どんどん興味が連鎖し、新しい発見や新しい視点に気づく感覚はなんだかとてもクセになります。
自分が少しでも興味を持ったことや好きなものは大切に。さらに深く、知りたい。そんな私の、ちょっと気になる関心ごとから始まるストーリーに今後もお付き合いください。
気象予報士
國本未華