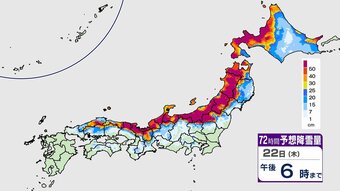長生炭鉱の水没事故による犠牲者の遺骨発掘を進めるため、炭鉱の排気筒から坑道に入れるかを確認する潜水調査が行われました。

1942年、山口県宇部市の長生炭鉱が水没する事故がありました。
朝鮮半島出身者136人を含む183人の労働者が犠牲になり、今も炭鉱の中に残されたままとなっています。

この事故の犠牲者の遺骨発掘を進めようと活動する市民団体と水中探検家の伊左治佳孝さんは、今も残る炭鉱の排気筒・「ピーヤ」から坑道に入れるかを探る潜水調査を行いました。
調査が行われたのは、2本あるうちの沖側の「ピーヤ」で、27年前の潜水調査では水深10メートルあたりまで潜り、突起物があることなどが確認されていました。

今回の調査で、ダイバーは水深27メートルの坑道の天井の高さとみられるあたりまで潜水。
この地点に「鋼管などの金属の構造物が積み重なっている」などと状況を話しました。

水中探検家 伊左治佳孝さん
「泥で埋まっているような感じではなかった、大きい構造物で埋まっているというか通れなくなっている感じだったので、それを引き上げさえすれば(坑道に)入れるのかなと」
長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会 共同代表 井上洋子さん
「(沖のピーヤの場所が)一番低い所になるんですね。一番低い場所に水がたまっていて、そこでみんなが逃げられなくなったというところなので、ピーヤからもし入れるということに次の段階でなったらそれはすごい成果につながるかなと思います」

今後、岸側の「ピーヤ」の潜水調査も行う予定です。
また、会では、秋ごろに炭鉱の入り口・坑口の開口も目指していて、「坑口」と「ピーヤ」の2つの入り口から遺骨発掘調査を進める方針です。