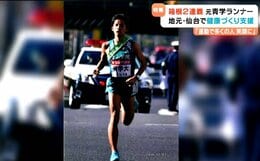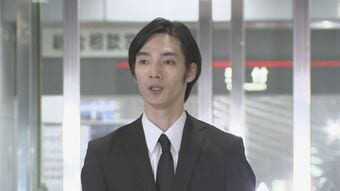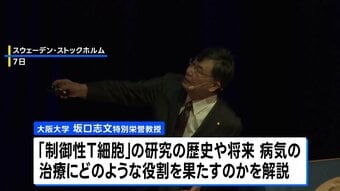長引く「円安」や、今年3月の日本銀行による金融政策の転換。今、日本の金融環境は歴史的な変化が起きています。17年ぶりの利上げをきっかけに「金利のある世界」に戻りつつある今、私たちの生活はどうなっていくのでしょうか。また、銀行の新たな生き残り戦略は。りそなホールディングスの南昌宏社長がJNNのインタビューに答えました。
どうなる?金利のある世界

──これまで日本では、超低金利が続いていてきました。そこから(3月の日銀による利上げをきっかけに)「金利がある世界」になると今後ビジネス面でも多くのことが変わってくると思います。今後をどのように考えていらっしゃるか教えてください。
まず、「金融政策の正常化に向けて入口に立った」という状況だと思いますけども、我々のビジネスにとっては基本的に追い風になってくるというふうに思ってます。
一つは、やはり国内の預貸金利益、中堅・中小企業・個人の皆様への円滑な資金提供というものをしっかり支えていくっていうこと。それから、これまでなかなか短い期間、5年債とかや中期債と言われているJGB(国債)のところに投資妙味(投資する醍醐味)がほとんどない状況が続いてたんですけども、ここに投資ができる状況になってきているっていうことが大きなポイントになってくると思います。
それから我々のビジネスで申し上げると、お客様の困りごとや、社会課題の起点を軸にもう一回、自分たちのビジネスを再構築しようという文脈の中で、これまで取り組みを強化してきた。その結果が、少しずつ出始めているところに、3月19日に金融政策の転換があって、少し、それが追い風、フォローの風になっていくっていう状況が深まってきている。そんな感じかなというふうに思ってます。
──金融業界での「追い風」という言葉はわかりやすいなと思ったんですけれども、具体的にこういう挑戦をしていきたいという思いはありますか。
まず、本当に我々はリテールNo.1を掲げてますので、中堅・中小企業・個人の皆様への円滑な資金提供、それからお客様の困りごとを起点として我々のコンサルティングビジネスをより深めていくっていうことが、本当にポイントだと思ってます。
──コンサルティング型で地力もついてきたというお話もいただきましたが、やはり「フィービジネス(手数料ビジネス)」と「双発型」で進めていかれるのでしょうか。
そうですね。2つのエンジンがようやく動き出すというタイミングに来たと思っていますので、それをしっかり結果に繋げていくってことが大事かなと思います。
──「双発型」についても詳しく聞かせてください。
まず本当に国内の預貸金利益ですね。一つは「預金の価値」。金利がついたことで、これまで以上に重要性が増してきている。
そして我々は元々安定的で粘着性の高い預金をベースに、(つまり)リテールの預金っていうものをしっかりベースに、どうやって運用していくのかっていうバランスシートマネジメントの中で当然生きてきた金融機関ですので、預貸率が低かった。
これってやはりどうしても運用サイドが金利が潰れていたりっていうことで投資妙味(投資する醍醐味)が薄かったっていうことが一つ大きな課題だったんですけども。これが少しずつ解消されてきているっていうのが今の状況かと思います。
なので、中期債を中心とする有価証券のところの復活もありますし、もとより国内の預貸金利益の強化、それからコンサルティングビジネスを強化していくことが、これからのビジネスを加速させていく上で大きなポイントだと思ってます。
──金利が上がることで中小企業の資金繰りが厳しくなるのではないでしょうか。インパクトは小さいとお考えですか。
まず金融政策の正常化に向けて、第一歩を踏み出した状況で、さほどマーケット金利が上昇しているわけでもありませんし、それから短期プライムレートがまだ動いている状況にはありませんので、大きなマイナスインパクトっていうのは、まだお客様に出ているっていう状況ではないと思います。
それから、もう一つ見方を変えると、リーマン・ショック後の中堅・中小企業の皆様の財務体質と足元の財務体質を比べると、やはり自己資本比率もそうですし、流動性比率、それから資本の厚み、こういったその財務的な指標っていうのは、かなり実は数十年前に比べて良くなってきてるんです。
なので、耐性もかなり中堅・中小企業の皆さんもお持ちになってきているので、変化にきちっと適応していくっていう流れの中にある企業様については、さほど大きなマイナスインパクトが出るような状況では今はないかなというふうに思ってます。
円安の影響は

──今、足元では円安の状況が続いています。この円安の影響は今のところどうみていますか。
円高か円安かという問題は、いつも何か出てくるんです。けれども、円高のときも、悪い円高とか、悪い円安のような、どっちにもやっぱりあるんですけども、一つはボラティリティの大きさっていうのは気をつける必要があると思っていますけれども。今、この1ドル=157円前後(※撮影当日の為替)の為替っていうのをどう考えるかっていうのは、当然プラス面もあれば、マイナス面もある。
これを今の日本経済に照らして、どの水準がいいのかっていう議論は別にあると思いますが、今の現状で特にマイナスインパクトが大きいのは、輸入物価が上がって、特にコストプッシュ型で物価が上がっていくことに対して、一般の国民の皆さんに対してはやっぱりマイナスインパクトっていうのが強くなってきている。
それから中堅・中小企業の皆さんについては原材料高だとか資源高っていうことも合わさって、かなり価格転嫁のところで、大企業さんに比べてやり方、スピードはかなり劣位しているところがありますので、こういったものが複合的に重なり合って、中堅・中小企業さんのところにやはりマイナスインパクトが出始めているっていうことは事実だと思いますので、これをどうやって凌いでいくのか、全体としてですね。
ただ一方で、GDPの問題であるとか、大企業さんの決算をご覧いただいて、かなり良い決算を出されているところも多いっていうこともあって、このバランスをやはりどうやって取っていくのかっていうことがこれから重要なポイントじゃないかなと思います。
──GDPの話も出ましたが、やはり個人消費は弱いですね。
そうですね。ここで所得の引き上げだとか、一部減税のような話もありますけども、これがどういうふうに消費増に繋がっていくのか、良い循環をどうやって作っていくのかっていうことについては国も企業も個人も一体となって考えていかなければいけないところだと思います。
──国民としては物価高で、賃上げもとなったときに価格転嫁で値上げが進んでいても、それを「会社側がどこまで従業員に落としてるか」というのはなかなか中小企業では厳しいなと思いますね。
ただ賃上げのスピードはかなり今回の春闘でも高かったと思いますし、少しずつ良い循環に向けて動き出しているという意味では一つ評価されてもいいのではないかなと思います。
長期金利の上昇は
──長期金利が11年12月以来ぐらいの水準まで上がっています。今すごく急速に上がっている印象ですが、どういう所感をお持ちですか。
(長期金利が)今の1%を超えた水準感っていうのは想定の範囲内だと思っています。緩やかにイールドカーブが上昇基調にあるということだと思いますし、一方で、短期のところっていうのは、まだ0から0.1というのが政策金利のところですので、次の日銀のアクションっていうのがどういう形になるかっていうことを我々が決める立場には当然ありませんけれども。
色々な変化を見据えて、予測と準備を怠らないこと。我々は色々なシミュレーションをしながら、どういう状況になっても機動的に動けるっていう状況をやっぱり作っていくっていうことが、今我々にできることですので、これをお客様目線でも考え続けるということが重要なところだと思います。