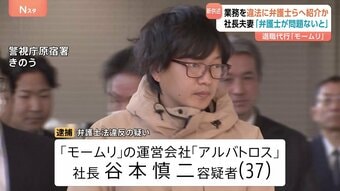握らないおにぎり・おにぎらずや拡大を続けるおにぎり専門店など、たびたびトレンド入りするお米。そんな日本の主食・お米をたくさん食べている都道府県TOP3を発表!
第3位 静岡県 72.98kg/年
第3位は「静岡県」。お茶の産地として有名な静岡県。お茶だけでなく山の幸や海の幸にも恵まれ、鮎の友釣り発祥の地とも言われています。また、1世帯あたりの米への支出金額では静岡が1位となっています。
第2位 新潟県 77.76kg/年
第2位は「新潟県」。米どころといえば新潟を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。米の作付け面積・収穫量ともに全国1位で、代表的な品種「コシヒカリ」は新潟県全域で生産されています。
第1位 福井県 77.16kg/年
第1位は「福井県」。福井での米の消費量を見てみると、1世帯あたり年間の消費量が全国平均(58.28kg/年)より約20kg多くお米を食べていることが分かりました。
鯖江市のめがねや越前ガニなどが有名な県ですが、
「福井といえば」に続けて「米」を挙げる人は少ないのではないでしょうか。
実際に米の生産量では全国上位に入らない福井県。
しかし、水田が耕地全体の91%を占めるだけでなく、農産物の販売をしている農家のうち84%が、米づくりをしています。
◆福井県は「コシヒカリ発祥の地」
スーパーなどでは新潟産コシヒカリを目にする機会が多く、コシヒカリは新潟が発祥だと思われている方は多いのではないでしょうか?
実はコシヒカリは福井県で誕生しました。
福井県HPによりますと、コシヒカリは1956年に福井県立農事試験場(現福井県農業試験場)で育成され、「越の国に光り輝く米」という願いを込めて命名されました。
◆日本で「食育」という言葉が初めて使われた地・福井
福井市HPによると、「食育」という言葉は福井県出身の石塚左玄という人物が日本で初めて提唱したといわれています。石塚左玄は医師と薬剤師の資格を有し、陸軍少将、陸軍薬剤監などとして活躍しました。
石塚左玄が1896年(明治29年)に著した「化学的食養長寿論」に、「学童を持つ人は、躰育も智育も才育もすべて食育にあると考えるべきである。」とし、食に関する知識や様々な経験の重要さを記しました。
左玄は著書の中で以下の「食の6つの訓え」を説いており、これは現在農林水産省の「食育基本法」の礎になったと言われています。
〈1〉家庭での食育の重要性 (食育は家庭教育)
〈2〉命は食にあるという考え(食養道)
〈3〉人間は穀食動物である (人は穀食動物)
〈4〉食物は丸ごと食べる (一物全体食)
〈5〉地産地消で地域の新鮮で旬のものを食べる (入郷従郷・身土不二)
〈6〉バランスのある食事 (平衡)
また、全国の高校生が食の知識や調理技術を競う「全国高校生食育王選手権」も福井県が開催しています。
実際に福井県出身者に話を聞いたところ、学校で稲作体験をしたり、学校が所有する水田で黒米を栽培・収穫し調理実習で食べていたというエピソードも。
食育の積極的な取り組みやお米に触れる体験が米の消費につながっているのかもしれません。
福井県出身者に聞いた!おすすめご飯のお供
「おぼろ昆布」
厚さ3ミリ以上の肉厚な1枚の昆布をカンナで削ったものを「おぼろ昆布」といいます。
とろろ昆布と似ていますが、とろろ昆布は厚さ3ミリ未満の昆布を束にして削ったものを言います。この2つは食感が異なり、おぼろ昆布はとろろ昆布に比べ、歯ごたえがあるのが特徴です。
味噌汁に入れてもよし。おにぎりに包んで食べてもよし!
福井県では海苔ではなくおぼろ昆布でおにぎりを包んで食べるのがポピュラーなんだそうです。

「鯖のへしこ」
若狭地域や越前海岸沿岸の伝統料理で、塩漬けしたサバを、こめぬかと塩で半年ほど漬けた発酵食品です。塩味と甘みが強いのが特徴で、お茶漬けや寿司のネタとしてはもちろん、最近ではチャーハンの具や、アンチョビのようにパスタやピザなどにも使われています。
ご紹介したランキングはいかがだったでしょうか?
円安状況が続くなかで米は円安の影響が少なく、値上げに繋がりにくい家計の味方。
お米製品を手に取る機会が増えてきそうです。
福井県民おすすめのおぼろ昆布おにぎりなど試してみてはいかがでしょうか。
※本ランキングは、総務省統計局 家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング・2021年~2023年平均を基に都道府県庁所在市と購入数量ベースで作成しています。