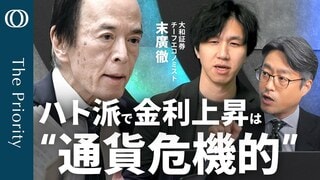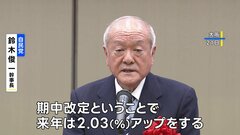(ブルームバーグ):住友生命保険は含み損が膨らんだ一部の国債について、簿価の水準に回復するまで保有する「保有継続」の措置を取ることを決めた。金利の低い時に購入した債券が、急激な金利上昇(債券価格は下落)によって大きな含み損が発生し、減損損失の計上リスクが高まったためだ。
関係者への取材で明らかになった。減損計上リスクを避けるために保有継続措置を取ったことが明らかになるのは大手生命保険会社では初めて。時価が著しく下がった債券を売却して損失を計上した上で資産を入れ替えるよりも、保有を継続して元本を回収した方が経済合理性が高いと判断した。保有継続とした具体的な金額については明らかになっていない。
生保各社は基本的に満期での保有を前提として国債などを購入している。ただ、保有債券の時価が取得価格を50%以上下回るなど回復の見込みがない場合は、評価差額を損失として計上することが現状の会計基準で定められている。
保有継続の措置を取ることで、減損基準に抵触したとしても損失を計上しなくて済む。一方、簿価水準に回復するまで売却することはできず、債券の入れ替えなど運用面で制約を抱えることにもなる。日本銀行による追加利上げも見込まれる中、各社の運用戦略がより問われる局面となる。

生保が主な投資対象とする30年債の国債利回りは9月に過去最高を記録した。大手生保4社の国内債券含み損は6月末時点で計9兆8300億円超にまで膨らんでいる。住友生命は国内債で1兆7103億円の含み損を抱え、株式を含めた有価証券全体でも3100億円の含み損だった。
住友生命・広報室は電子メールで、保有継続の措置についてのコメントを控えた上で「健全性に問題はなく、大幅な金利上昇に備えたストレステストなども実施し、リスク管理を徹底している」と説明した。
今期(2026年3月期)末から適用される新たな資本規制では、資産として抱える国債などと同様に負債として抱える保険契約も時価で評価する。金利上昇で資産、負債ともに価値が下落するため、両者の平均残存期間が一致していれば、含み損が拡大したとしても健全性を示す指標には問題ないとされる。
野村証券の田平泰啓ストラテジストは「会社全体でみれば含み損を維持することは経済合理的に問題ない」として、さらに金利が上昇すれば、保有継続を選択する生保は増えてくる可能性もあるとの見方を示した。
一方、含み損を抱えたままだと「運用の制約になってしまう」としたほか、より収益性の高い資産を保有している方が、より高い利回りの保険商品を提供できるとして、中長期的には商品戦略にも影響を与える可能性にも言及した。
(市場関係者のコメントなど第7段落以降を追加します)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.