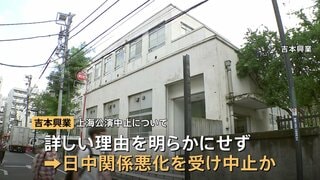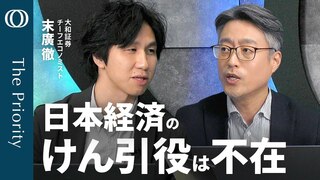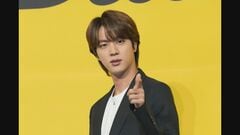(ブルームバーグ):日本銀行の内田真一副総裁は5日、日銀の経済・物価の見通しが実現していけば利上げを続けるとし、経済を確認しながら進めることが可能であるとの見解を示した。静岡県金融経済懇談会で講演した。
内田副総裁は今後の利上げパス(経路)に関し、日銀の経済・物価見通しが実現していけば引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく方針を改めて表明した。経済・物価に中立的な実質金利である自然利子率の推計は幅が広すぎて「実際の政策運営には使えない」とした上で、想定される利上げペースであれば、「経済の反応を確認しながら進めていける」と語った。
日銀見通しのポイントは、2%の物価安定目標を実現できると予想していることだと説明。基調的な物価上昇率は足元で2%を下回っているものの、賃金上昇を伴う形で2%に向けて上昇していくとし、来年度後半から2026年度中の1年半のどこかで「現実の物価と基調的な物価が共に2%程度になる」と語った。
日銀の1月利上げ以降も、政策委員の追加利上げに前向きな発言や良好な経済指標などを背景に、市場では早期利上げ観測が浮上している。内田氏の今回の講演では、今後の利上げはあくまで経済の反応を見極めながら進めていく方針が示され、時期やペースを示唆するような発言はなかった。
みずほ証券の松尾勇佑シニアマーケットエコノミストはリポートで、内田副総裁は市場が想定する半年に1回程度の利上げペースに違和感を持っていないとみられ、「現時点ではおそらく、利上げペースを加速させることを想定していない」と指摘。次の利上げは7月か9月の会合と予想し、慎重に検討する意味でも「9月会合の可能性の方がやや高い」とみている。
内田氏は午後の記者会見で、想定される利上げペースの具体的内容について問われ、「特定のペースを念頭に置いたものではない」と説明。「市場の見通しのことを言っているわけでもないし、例えば日銀が考えている見通しのことを言っているわけでもない」と述べた。
日銀による追加利上げ観測などを背景に長期金利は上昇基調にあり、5日は前日比2.5ベーシスポイント(bp)高い1.445%となった。日銀は昨年7月の金融政策決定会合で決めた国債買い入れの減額計画に沿って段階的に購入を減らしているが、期限の26年3月でも500兆円を超える残高が維持される見通しだ。
内田氏は講演で、国債買い入れについて、残高ベースの減少はわずかなので「引き続き大きな緩和効果を有している」と指摘。長期金利は市場で自由に形成されることが基本とした上で、急激に上昇する例外的な状況では機動的に増額などを行うという考え方は「現在でも有効」とした。
トランプ政権
内田氏は、米国の新政権の政策など経済・物価双方に影響しうる事象があり、地政学的な緊張も高い状況が続いていると指摘。こうした要因の帰すうや予想は各国の企業・家計のコンフィデンスや国際金融資本市場の動向などに影響するとし、「世界経済についての不確実性は高く、引き続き十分注視していく」と語った。
トランプ米大統領は3日、日本と中国が通貨安政策を取るなら米国は「不当に不利な立場に置かれる」と述べるとともに、そのような場合、関税措置を講じる可能性を示唆した。発言を受けて、市場では円安回避を念頭に日銀の金融政策への影響を警戒する声も出ている。
内田氏は会見で米政権の関税政策の影響について、当然ながら日本の経済・物価に影響するとしながらも、金融政策運営に当たっては米経済や為替の影響を含めて「日本の経済・物価を考え、政策を打っていくということに尽きる」と指摘。これまでの大規模緩和も「特に為替の誘導を意図したということはない」と語った。
1月の金融政策決定会合では政策金利を17年ぶりの0.5%程度に引き上げ、経済・物価が見通し通り推移すれば利上げで緩和度合いを調整する方針を維持した。経済・物価情勢の展望(展望リポート)の消費者物価見通しを、25年度を2.4%に引き上げるなど上方修正するとともに、24年度と25年度は上振れリスクの方が大きいとした。
会見では、物価の基調を考える上で最も重要なのは賃金だとし、購入頻度が高い品目の動向を含めて人々の物価予想に及ぼす影響を十分注視していかなければならないと説明。その上で、賃上げ率が高ければ高いほど物価の基調を引き上げる可能性が高く、日銀の見通し実現確度が上がるとしつつ、金融政策はその他をことを含めた総合判断だと繰り返した。
(午後の記者会見での発言とエコノミストコメントを追加して更新しました)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.