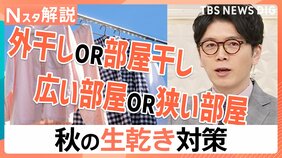通説「食あたり」は間違い
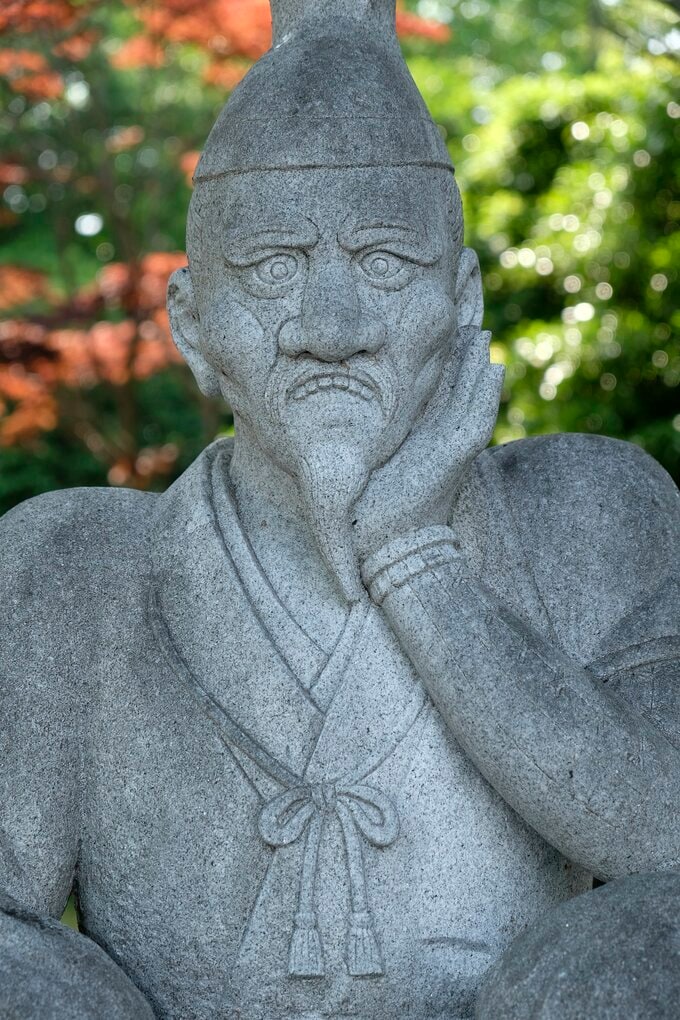
江戸幕府の公式史書『徳川実紀』には「1616年1月21日、藤枝市で鷹狩をして、夕飯に京都で流行っていた鯛(タイ)の天ぷらを食べたところ、翌日の午前2時ごろ腹痛を訴え、医者の診察により腹部のしこりが見つかった」という記述があります。後に「家康公は天ぷらを食べ過ぎて食あたりで死んだ」という通説の元になる記録ですが、静岡市の「県立大学前クリニック」の医院長で長年がん治療に携わってきた松田巌医師は「食あたりではなく、原因は家康が健康オタクだったことと関係が深い」と推論します。松田医師と『徳川実紀』をひもとき、家康公の真の死因に迫りました。
「しこり」から胃がんを見抜く

「食あたりとは急性胃腸炎、もしくは食中毒を指し、腹痛や嘔吐(おうと)下痢を起こす急性疾患です。夕飯に天ぷらを食べて就寝後に発症するという時間経過は妥当です」と話す松田先生は食あたりとは決定的に違うポイント指摘します。「しこりは食あたりではできません。お腹のあたりに外から触って分かるほどのしこりがあったということは別の病気の可能性を示唆しています。場所からすると胃がん、しかもかなり進行した胃がんだったと想像できます」。家康公はかやの油で揚げた鯛にニラをかけて食べたとされていますが、天ぷらによる消化不良が、潜在していたがんの症状を顕在化させた、というのが正しいようです。