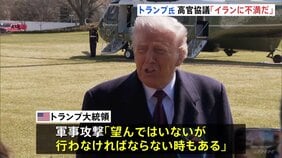患者と家族を面会させない理由は「ない」

小野寺:他の病院のことを、「お前の病院は」というふうには、なかなか言えないですよね。面会制限も、面会する人が無症状で、患者が感染症に対して特にリスクが高くなければ、「面会させない」理由は本当はないんですよね。しかも、入院している人は、お年寄りがほとんどです。お年寄りは、家族に会うことができなければ、病院にいてもどんどん弱ってしまいます。家族が会うことは非常に大切なことなので、それができない病院は、療養の環境としては非常にレベルが低いということになります。だから、それはなんとかしたいという思いは、コロナの流行当初からありました。
野路:静岡市立静岡病院では、面会の制限はないのですか?
小野寺:ありません。面会する人を家族に限っていた時期はありました。最近は患者さんが皆さん元気で、面会時間が長く、にぎやかになって苦情が出てきたので、30分間ぐらいにしてもらおうかという話もあったのですが、今も制限はしていません。一方で、いわゆる儀礼的なお見舞いは控えてもらっています。会社の上司が入院しているから、顔を出しておこうかなというケースです。これは、コロナ禍に“便乗”した形で、控えてもらうようにしました。
野路:マスクの着用についてはどうですか?
小野寺:マスクの着用を広く呼びかけることは、していません。「せきチケット」はやはり大切だと思っていますから、ゴホゴホしながら来られるならマスクはしてもらわないといけないと思います。手洗いもした方がいいです。しかし、普通の状況では、院内でマスクをする必要はないと考えています。
日本の組織「話し合いを避け ルールを増やし 張り紙だらけ」
磯野:「ハリネズミ」のようになってしまうとか、面会で羽目を外しすぎる方がいて「30分にしようとした」といった話を伺って、何か個別の問題が起きた時に、その人に対して「やめてください」ということが非常に言いづらい社会だと思いました。個別のクレーム処理が苦手なんですね。日本社会が全体的に抱える問題といえると思います。
とにかく事を荒立てたくない。個別の干渉はしたくない。だから個別の問題が起こると、全体のガバナンスの問題にまで事を広げ、張り紙をしたり、ルールを増やすなどして、全体に向けての発信を行う。別の個別の問題が起きたら、全体に対してさらにルールを増やして、それを張り紙で掲示する。一方で、ルールを減らすことはできません。「何かあったらどうするんだ」といわれると、足がすくんでしまうからです。こうしてルールだらけ、張り紙だらけの組織が出来上がります。
話し合いが大切といわれますが、話し合える社会にしていくのであれば、何か問題が起きた時に、きちんとその問題に対して議論し、調整をするべきだと思います。問題が起こるたびにルールを厳しくし続ける姿勢からは、議論は生まれません。コロナ禍の過度な感染対策は、そのような状態がずっと続いてしまった結果ではないでしょうか。
小野寺:そうですね。人と直接ぶつかりたくないというのは、よく分かります。初めから先回りをして、後から文句を言われても大丈夫なようにしておこうということですね。難しいでしょうが、人とぶつかることを怖がらないようにというのは、していくべきなのかもしれません。
磯野:医療者にインタビューすると、理不尽なことで病院が責められて、和解金を何百万円払ったといったことをしばしば聞きます。訴訟に発展するようなもめ事の時に、「こういうことは起こってしまうことなんです」などと交渉すること自体が、個人の道徳感や胆力があるかないかの問題ではなく、慣習的に非常に難しい社会なんだろうなと思いますね。
小野寺:医療訴訟は理不尽な事柄もありますが、自分が被害を受けたと思っている方にしてみれば、それは非常に怒りなどがあるわけで、そこを理解はした方がいいと思います。ただ、医療者にとっては、リスクを説明した上でまともな治療をしたのに、体にダメージが起きたと訴えられたら、説明をしていくしかないですね。
磯野:こういう話がありました。入院していて、ある程度回復した高齢者が、1日外泊をして、自宅で団子を食べた。すると団子を喉に詰まらせて亡くなってしまった。こんなことになったのは外泊をさせた病院の責任だと、家族が激怒して、結果的に病院が慰謝料を払うことになったと。めったにない事例かもしれませんが、そのようなことが一つでもあると、医療側としては構えてしまいますよね。入院患者が家族と外出する時に、外出先で食事をして、病院に帰って来た時に何か問題が起きると困るから、とにかく食事は病院で取ってくださいと。そのようなルールを設けている病院があると、最近聞きました。
「気の緩み」のせいにした反省を
野路:コロナ禍の行き過ぎた感染対策などを反省点として、教訓として生かしていくためには、何が必要でしょうか?
小野寺:今回の行き過ぎた対策の弊害は、実はまだ残っているわけです。例えば、子どもの成長を考える時に、一日中ずっとマスクをしていて、友達はできたのかな。大学もリモートで講義して、学生の身についたのかな。そういった社会に対するダメージは続いていて、これからかなり影響が現れてくるのではないかという気がします。
磯野:教育現場という観点からいうと、コロナ禍以前とコロナ禍後の、学生の講義の受け方が変化したと思います。学生がメモを取らないんです。ノートも開かない学生が一定数、出てくるようになりました。リモート講義では、学生はずっと画面を見ていて、録画も残るので、リアルタイムで聞いていなくても後で巻き戻せばいいから、というわけです。メモを取らない学生に私は衝撃を受けました。やはり体を動かすことで身につくものはあると思っていますが、それすらしない学生が出てきたなと。
そして、次のパンデミックに生かしたい今回の問題点は、感染が拡大すると、メディアを通じて必ず「気の緩みのせいで感染拡大した」といわれたことです。コロナは流行の波があって、おそらくインフルエンザのように周期的に訪れるものだと思います。それを我々の“自覚”の問題であると言いすぎないことは、私は非常に重要だと思います。「気の緩んだ国民」と「現場で必死に闘っている医療者」という対立構造が生まれたことで、病院のオペレーションがうまく機能せず、医療が逼迫しているという問題の本質に目が向きにくくなり、結果的に対応が遅れたと思います。いつまでも保健所が濃厚接触者を追い続けるなど、感染対策を過剰にしてしまった結果、現場が大変になるということもありました。それを、「気の緩み」のせいとか「自覚のない人」のせいにしてしまうと、そこにある具体的な問題点が見えなくなります。「気の緩み」を持ち出す報道は、次回は控えてほしいです。
小野寺:国内で最初にコロナの感染が始まった頃は、コロナにかかった人は「極悪非道の大悪人」だという風潮がありましたね。「あの人は東京に行ったからコロナにかかった。帰ってくるな」という話が出てきたわけです。最初から感染を封じ込めることは不可能だったのに、それでも「かかった人は悪い人」「帰省した人は悪い人」「他県のナンバーの車で走るな」。実際に石を投げられたりして、「私は◯◯県民です」と車にステッカーを張ったりする動きもありました。日本人の特性だから、という見方もあるかもしれませんが、次にパンデミックが起きたときにはマスコミなどが、「前の新型コロナの時にはこんなことがありましたが、こういうことはしないように」と、それこそコロナ禍に起きたことを振り返る機会を作っていただいて、ヒステリーにならないようにしていただきたいと思います。
野路:もちろん、感染対策は皆さん、真面目な気持ちで取り組んできたことですが、通り過ぎてみると、真面目にやっても「これはやりすぎたな」と思えることはいくつもあるのではないでしょうか。そこを冷静に受け止めて、教訓として、心に留めておきたいですよね。
<2人の略歴>
小野寺知哉(おのでら・ともや)
京都大医学部循環器内科臨床教授。循環器専門医。総合内科専門医。京都大医学部卒。同大医学研究科修了。米国シンシナチ大客員研究員などを経て1990年から静岡市立静岡病院勤務。2019年から病院長。23年から理事長兼務。25年4月から理事長専任
磯野真穂(いその・まほ)
東京科学大(旧 東京医科歯科大・東京工業大)リベラルアーツ研究教育院教授。早稲田大卒。オレゴン州立大大学院などで学び博士号(文学)取得。応用人類学研究所・ANTHRO所長。著書に『コロナ禍と出会い直す』『他者と生きる』など
(2025年3月21日にYouTubeチャンネル「SBSnews6」で配信した『面会制限やマスク…過度な感染対策いち早くやめた 静岡市立静岡病院長が医療人類学者とこの5年を振り返る』を基に追加取材して一部加筆、再編集しました)