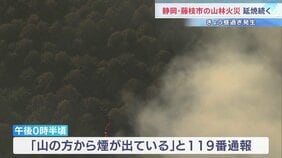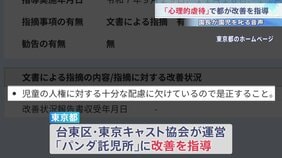子どものころ、みな一度はあこがれるであろうクワガタムシ。カッコ良さのシンボル「大顎」の謎を解明しようと静岡大学で研究が進んでいますが、いま、クラウドファンディングで支援が呼びかけています。その背景にあるのは深刻な研究費不足です。
<小学生>
「ギラファノコギリクワガタは長い顎がかっこいい」
静岡県磐田市の竜洋昆虫自然観察公園では、世界中から集められた約30種類のクワガタが展示されています。多くの人の心をわしづかみにするクワガタのシンボルは、ハサミの形をした大顎です。
<磐田市竜洋昆虫自然観察公園 荒井克也さん>
「種類によって、それぞれ見てみると大顎の形も違って、かっこいいものから変な形のものもいたりするので、違いも魅力」
なぜ、オスのクワガタは大きな顎が発達しているのか。その理由を遺伝子レベルで解明しようという研究が静岡大学で進んでいます。
<静岡大学理学部 後藤寛貴助教>
「例えばこの辺がクワガタムシの成虫になります」
静岡大学理学部助教の後藤寛貴さんは、大学院時代から20年近くクワガタの研究を続けてきました。
<後藤助教>
「生物学としてハサミの部分、大顎の部分。どんな虫でもあるのですが、そこだけをオスだけででかくする仕組みが不思議だなと」
誰もが知っているクワガタですが、実は生物学的な研究はあまり進んでいません。
<後藤助教と学生>
「オスがこれですね、6日目のやつで」
「ああ、できてるね」
後藤さんは、クワガタに興味をもった学生ら15人とチームを組んで本格的なクワガタの研究を進めています。
<学生>
「クワガタは誰でも知ってるんですけど、自分が研究したことがすべて新しいことというのが中々ない経験」
後藤さんと学生たちは、顎の発達に遺伝子が関わっているのではないかと仮定し、遺伝子操作などで謎の解明に取り組んでいますが、大きな悩みがあります。
<後藤助教>
「外部から研究費を取ってこないと、学生にまともに研究させられなくなっているのが大きな問題になってまして」
国立大学は独立法人化されて以降、国からの交付金が減り、資金の確保が大きな課題となっています。後藤さんの場合、2024年度、600万円ほどあった研究費が、2025年度は100万円くらいまで減少。壊れた実験設備もいまは放置されたままです。
この状況を打破しようと後藤さんらが頼ったのがクラウドファンディング。実験の設備や薬品の購入などを目的に、2月20日までに200万円を集めたいとしています。
<後藤助教>
「科学というのは本質的に面白いものだと一般の人々に知ってもらいたい。基礎研究に応援する気持ちを持ってもらえると、大学にもっと予算を入れようという世論につながるんじゃないかと」
後藤さんらの研究チームは、クラウドファンディングで集まった資金を使い、2025年4月から研究を加速させ、2026年9月には、学会でクワガタの研究結果を発表したいとしています。