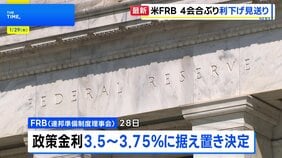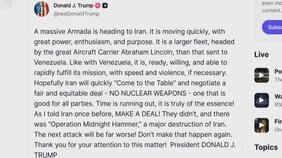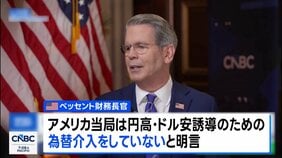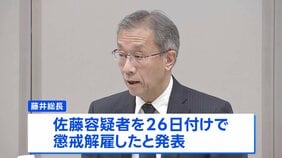論文の引用回数が多く、ノーベル賞級の研究をしたと評価される今年の「クラリベイト引用栄誉賞」に、信州大学の堂免一成(どうめん・かずなり)特別特任教授が選ばれました。

「クラリベイト引用栄誉賞」は、イギリスの情報会社が論文のデータベースを基にして影響力のある研究者を選ぶもので、今年は6か国を拠点とする22人が選ばれました。
このうち日本人は、信州大学アクア・リジェネレーション機構の堂免一成(どうめん・かずなり)特別特任教授と、アメリカ国立眼病研究所の彦坂興秀(ひこさか・おきひで)博士の2人です。
堂免特別特任教授は、二酸化炭素を排出しない、太陽光を利用した水分解による水素の生成に関する研究を、長年にわたり進めてきました。
信州大学によりますと、水の分解に使う粉末の光触媒は、シンプルな構造で大規模な展開が可能なため、実用化に向けた可能性を秘めているということです。

太陽エネルギーの効率的な利用には、可視光線に反応する光触媒の開発が重要で、今後、飯田市の5,000平方メートルの土地に水分解パネルを設置し、国内最大級の実証試験を行う予定です。
堂免特別特任教授は、大学を通じて「受賞は大変名誉なことですが、この技術を社会実装し、大規模展開するにはまだ解決しなければならない問題がいくつかあります。なかでも光触媒の効率向上は喫緊の課題であり、今後2、3年程度で実用レベルまで改良していく予定です」とコメントを出し、飯田市での実験が非常に大きなサポートになるとの認識を示しました。
「クラリベイト引用栄誉賞(旧トムソン・ロイター引用栄誉賞)」には、ノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥(やまなか・しんや)さんや大隅良典(おおすみ・よしのり)さん、本庶佑(ほんじょ・たすく)さん、物理学賞を受賞した中村修二(なかむら・しゅうじ)さんなどが過去に選ばれていて、ノーベル賞級の研究として評価されています。