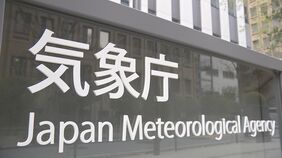ハンセン病の歴史 7世紀の「日本書紀」に記載がある
(山本典良園長)
「ハンセン病の歴史について、簡単に話をしようと思っています。ハンセン病、目に見える病気なので、7世紀の『日本書紀』に記載があるのです。
おそらく、その時代にも胃の病気とかね、肝臓の病気、腎臓の病気、いろいろな病気があったと思います。でも、目に見えないので、分からないのですね。ところがハンセン病は、目に見える病気なので、7世紀の時点で、これはハンセン病だけじゃないと思うんですけど、忌むべき病として認知され、そこから、社会からの排除が始まるのです。
日本でなぜ偏見差別が強くなったかというと、仏教的な考え方からです。北山十八間戸(鎌倉時代、奈良につくられたハンセン病などの重病者を救済した福祉施設)のように、救済する一部の仏教宗派はありましたけど、大体は迫害というか、排除していた。
因果応報、業病、天刑病。前世に悪いことをしたからハンセン病になったんだとか、天からの罰だと。これはどういう教えかというと、悪いことをしたらハンセン病になるから悪いことするのをやめましょうという教えですね。ですから、ハンセン病になった人は救われません。悪いことしてハンセン病になったのだから天からの罰だと言われたら救いようがないですね。
それとちょっと違うのはクリスチャン、キリスト教ですね。キリスト教は、旧約聖書はいわゆる排除ですね。イエス・キリストの新約聖書からは、イエス・キリストが皮膚病の人を触ったら治ったということで、救済に回るのです。
ところが、江戸時代に鎖国があり、キリスト教は迫害され消滅したということで、あまりハンセン病患者を救う人たちがいなかった。
江戸時代は、患者の生計というのは神社仏閣の参道門前、家を回っての物乞いによっていました。江戸幕府になって、幕府の統制が弱まって人々の移動が可能になると、放浪するようになった。『放浪らい』ということになる。患者が放浪して、町中にあふれるわけですね。
その人たちを誰が最初に救ったかというと、宣教師です。クリスチャンです。なぜクリスチャンが救えたかというと、彼ら欧米の、環境状態のいいところから来てくるわけです。彼等が信じている宗教を、いわゆる未開の地に行って広めるようなものです。
その人たちの母国では、もうハンセン病患者はいません。特効薬ができる前に、いなくなっているのです。でも、新約聖書にはハンセン病のことを書いています。その患者さんを日本で見つけるんです。ハンセン病患者を。見かけた時にどう思うのかなと想像してみたら、おそらく、これはイエス・キリストが我々に与えた試練だと多分思うのですね、宣教師は。
ですから、母国から寄付を募って療養所、いわゆる救済のために診療所を作ります。そのように、大体クリスチャンが作っていた。そういう状況が続いた。
やはり、文明国というのは、ハンセン病患者を放っておくなという考え方です。文明国、一等国であればハンセン病を何とかしようということになって、1907年『癩予防ニ関スル件』ができて、『放浪らい』を、療養所に入所させました。
放浪する患者たちを一般社会から隔離しました。放浪していますから、明日の、今日の食事とか、雨が降ったらどうしようとか、困っている人たちに、衣食住を与えて、しかも治療をしようということで、救済とするので、ひとまずはいい面でもありました。
ですが、ハンセン病は伝染力が強いとか、誤った考えが広まりました。1909年に公立5か所、近くでは、高松がそうですけど。この5か所の5人の所長中4人が警察出身でした。医者は1人しかいなかったということで、どう考えても犯罪者扱いでしょう。
1929年、30年頃になって、やっぱり軍国主義というかね、そちらの方に国が走って『無らい県運動』はこの頃に全国的に進められて、1931年に『癩予防法』ができた。これは強制隔離でハンセン病絶滅政策、在宅患者も療養所へ強制的に収容されるようになったということです」