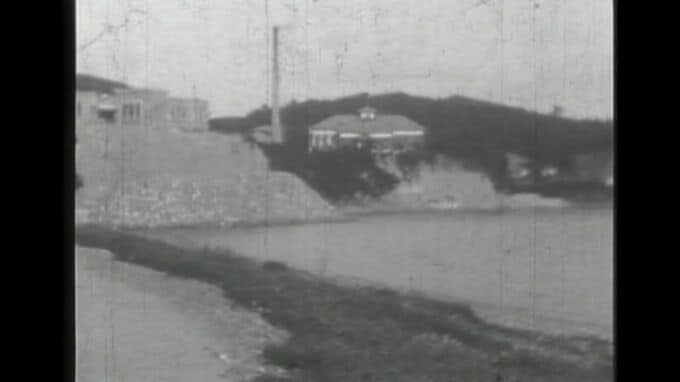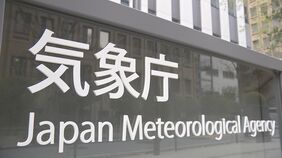「ハンセン病」を理解してもらいにくい時代
(山本典良園長)
「 令和7年3月24日、岡山県ハンセン病問題対策協議会があって、岡山県のホームページで(議事録が)見られるのですけど、そこで、中尾さんはこう発言しました。
『ハンセン病というものを理解してもらうのが難しくなってきました』と。若い人がハンセン病を知らないということですね。
中尾さんは『若い人たちにハンセン病を知ってもらうため、昔の悪い状態の写真等を出した方が良いかと思うこともあります。なぜハンセン病が嫌われたかを話す方が分かってもらいやすいなどと思い迷っているところがあります。自分の体験したことははっきりと伝えるようにしていますが、昔の怖い状態であったことをどのように伝えれば良いのか考えていってもらった方が良いと思います』と発言されています。
実は、昔の教科書には、ハンセン病患者はこんな状態だったという写真が掲載されています。(皮膚から膿が出たり、指が欠けたりしている)
現状は、全国13箇所に(国立)ハンセン病療養所があります。7月31日現在、609名が入所されています。平均年齢88.8歳です。愛生園は67名です。男性34名、女性33名、平均年齢89.2歳です。
病棟で治療が必要な方は5名。介護棟で介護が必要な方が42名。一般舎といって、身の回りのことできる方が20名いらっしゃいます。中尾さんは一般舎に住んでおられます。
一番若い方では男性が73歳。最高齢は、100歳の女性がいらっしゃいます。平均在園年数62.9年、ほぼ63年ですね。ハンセン病は幼少期に感染して思春期に発症して、それから療養所に送り込まれるということで、平均が63年です。
実は、ハンセン病療養所、長島愛生園には、日本で初めてというのが3つあるかなと思っています。
1つは、患者の会です。いま、乳がんとか、いろいろな患者の会があると思います。その最初はおそらくは、ハンセン病療養所の患者の会。日本で最初の患者の会です。
2番目は、院内学級。いま、総合病院では、児童が入院したら院内学級という教育をする施設があります。実は、ハンセン病療養所には、小学校、中学校はありました。
乳幼児期に感染して思春期に発症して入所するので、どうしても小学生、中学生の教育をしないといけないということで、最初は入所者が先生になって教え、戦後、義務教育になって、小学校、中学校は、各地の療養所内にありました。分校という形で。
愛生園には高校がありました。岡山県立邑久高等学校の新良田教室、新良田分校ですね。これは、4年制です。午前中、授業をして午後は治療を受けたり、園内作業をしたりということで4年かけて卒業する。
今後、病院の中に高校ができることがあり得るかというと、もう絶対にあり得ないと思います。義務教育は、義務だからある程度、できる可能性があるかもしれない。でも、高校は、義務教育じゃない。それが病院の中にできることは、絶対ありえないです。
ですから、もう今後もありえないものが唯一無二で長島愛生園にあった。高校があったのは愛生園だけです。ハンセン病療養所が13ある中で、長島愛生園しかなかった。
昭和28年に『癩予防法』が『らい予防法』に改正されて強制隔離が続いたのですけど。患者さんの教育改善ということで昭和30年から入学が始まって昭和62年まで卒業生がありました。
1学年30名です。29期生まであったのですね。入学が369名、卒業が307名で、社会復帰が225名で、7割の方は社会復帰されています。ドクターもいれば弁護士になった方もいらっしゃいます。大学の教授もいらっしゃったそうです。でも、邑久高校新良田教室卒だというのはいえなかったんです。
あと3番目は、患者売店がありました。いま、病院には売店がありますね。おそらく最初は昭和5年に愛生園にできた患者さん専用の売店です。これがおそらく、日本初で、愛生園に残っているということです」