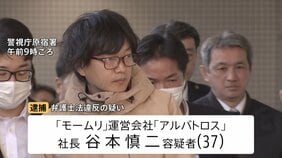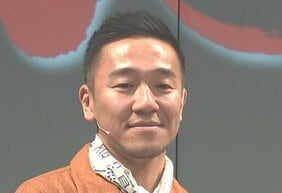近年、被害の報告が急増している「トコジラミ」。
「一生人の血を吸う」トコジラミには弱点があった!
被害にあわないためにはどうしたらよいのでしょうか。害虫対策などを手掛ける、岡山市の東洋産業・大野竜徳さんに「トコジラミ」の性質や対策について聞きました。
ートコジラミはどんな虫なのでしょうか?
(東洋産業 大野竜徳さん)
「トコジラミは『シラミ』という名前がついていますが、実はカメムシの仲間で、別名『ナンキンムシ』とも呼ばれます。
カメムシの仲間は、植物や動物から体液を吸って生きています。トコジラミの場合、なんと主に『ヒトの血』を吸います。オスとメスがいますが『どちらも一生血を吸う』のです。しかも、こっそりみなさんが寝静まって暗くなった夜間、特に深夜にです。
明るい時間に出てくると目立って駆除されてしまうので、真っ暗な中、呼気中の二酸化炭素や体温を頼りに、吸血源を探します。吸血しない状態が2週間以上続いてお腹が減ってくると昼間にも出現しますが、通常は光を嫌うため、夜間でも照明がある場合には隠れて出てきません」
ー目視できる大きさなのでしょうか?
(東洋産業 大野竜徳さん)
「卵が1mm、幼虫は1.5~5.5mm、成虫は6~8mm、上から見ると小判型で意外と大きいので目に見えます。でも横から見ると薄っぺらく、1mmの隙間があれば隙間に隠れてしまいます」
【画像①】は、そのトコジラミの超アップ。上記の大きさを想像しながらご覧ください。

トコジラミは「カメムシ臭」がするという...
そんなトコジラミ、より深く知りたい方は、【画像②】に卵の写真もあります。そして成虫にはこんな特徴もあるそうです。

(東洋産業 大野竜徳さん)
「翅(はね)はなく飛ばないし、跳ねません。吸血は真っ暗な中、こっそりと素早く寄ってきます。でも、カメムシの仲間なので独特のカメムシ臭がします」
ーということは、「カメムシ臭」がするかどうかが発見の手がかりになりますね。
「たくさんいると、うっすら『カメムシ臭』がすることもありますが、残念ながらにおいよりも気づくのは『被害にあってから』の場合がほとんどです。