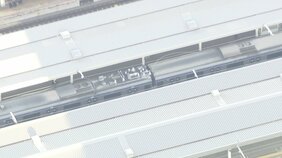見ていますか?ハザードマップ
自治体は、まずはハザードマップで自分が住んでいる場所の危険性を確認しておくことが大切だと話します。

熊本市 防災対策課 吉永浩伸審議員「避難というのは難を逃れるということになるので、避難が必要ない方はやっぱりいらっしゃる。避難が必要かどうかをまずは知っていただきたい。本当に自分が安全なのか、安全なところに住んでいるのかどうか考えて、『今まで大丈夫だったから』という考えはもう持たないでいただきたい」

「避難を自分事に」は簡単ではない
災害の危険性を知る上で重要な判断の基準となるハザードマップを、実際に街の人に見てもらいました。
「ピンクだったら浸水想定が3m~5m未満。初めて見ました」(30代)
「怖いですね、ちょっとやっぱり」(20代)

初めて知る自宅の災害リスクに驚く人がいる一方で、実感がわかないという人もいました。
「赤いね。近くに江津湖があるけんかな?」(10代)
「だけど、危険感じたことないから実感もわかないし、わからない」(10代)

全国で頻発する豪雨災害を「自分の身に起こるかもしれない」と考えて避難に繋げることは、心理学の分野から防災を考える“防災心理学”の観点でも簡単ではなさそうです。
防災心理学が専門 京都大学 矢守克也 教授「人は常に今やっていることをそのまま続けることが一番快適。快適な家から離れて避難する場合、相当大きな力で背中を押されないと、避難というアクションに移れないのが普通」
では、どうすれば私たちは『逃げるスイッチ』をオンにできるのでしょうか。