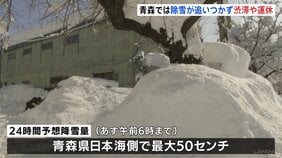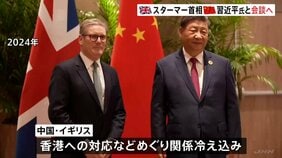ブラック校則が社会問題化する中、教育現場では「見直し」の動きも進んでいます。しかしその見直しは、「本物」でしょうか。「校則を見直した」学校も、その中身をみると実に様々。「見直す」ってどういうこと?
◆追及続ける弁護士 「校則やめます」となぜ言えないのか」

ブラック校則に関する相談を全国から受け付けている後藤富和弁護士。福岡県久留米市で開かれた「子供の人権」や「校則」について考える講演会で、語気を強めて訴えました。
後藤富和弁護士
「勝手に大人が決めた服のせいで学校に行けない生徒がいる。親や教師がすべきことは子供の権利を予め奪うことではなくて、子供が十分に自由を行使できるよう手助けすることではないか」
後藤弁護士は、合理的な理由がないいわゆる「ブラック校則」に悩み不登校になった学生らを継続して支援してきました。
後藤富和弁護士
「あのむちゃくちゃな校則を作り上げてきたのは大人なんです。だったら子供の意見を聞くまでもなく大人が反省して『もうやめます』が、何でそれが出来ないのかということなんです
ブラック校則が社会問題化する中、教育現場では少しづつ「見直し」の動きも出ています。しかし問題を追及してきた弁護士たちは、その見直しは十分ではないと指摘します。
◆靴下の長さはなぜ必要か

例えば、福岡県内では今年2月、ブラック校則の見直しを進めていた福岡市教育委員会が、「見直しは全て完了した」と発表しました。しかし「眉毛を剃ってはいけない、いじってはいけない」という規定や「くるぶし丈の靴下は不可」など靴下に関する細かな規定が依然残ったままの学校もあります。
佐川民弁護士
「靴下の色が白一色だったのが白と黒と紺とグレーから選べるようになったとか、言っていますが、しかしそもそもなぜ靴や靴下の色を指定しなければならないのか。その見直しまでにはいたっていない。自由に子供が意見が言える雰囲気まで含めて議論の場を提供しないと、本当の意味での子供が参加しての校則の検討にはならないと思っています」